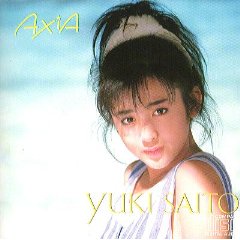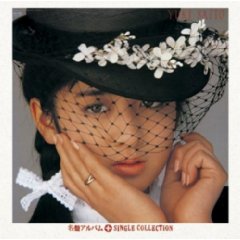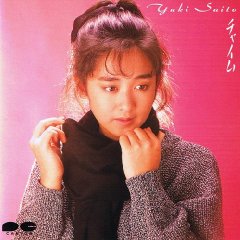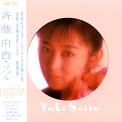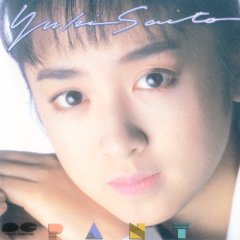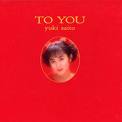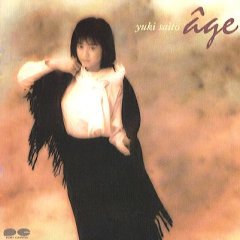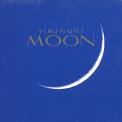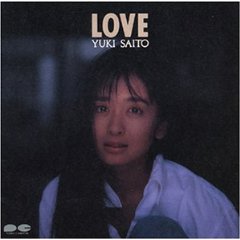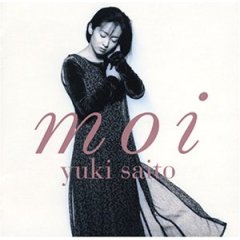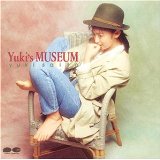 85年組のラッキーガール、斉藤由貴。アイドル時代の彼女はとにもかくにも引きが強かった。
85年組のラッキーガール、斉藤由貴。アイドル時代の彼女はとにもかくにも引きが強かった。雪模様をバックに、学校指定といった地味な紺のコートと対照的な真っ赤なマフラーを首に巻き、暗い瞳をした少女が、思いつめたようにぽつりとつぶやく。"胸騒ぎを、ください" この明星食品「青春という名のラーメン」のCF一本で斉藤由貴はアイドルのスターダムにのし上がった(――第2弾の学生服の波をひとりだけ振りかえった斉藤由貴の"誘惑しても、いいですか"もよかったよなぁ)。 その直後のデビューシングルは松本隆+筒美京平の渾身の一撃でいきなりの大ヒット。レコードでも初速で同期の他のアイドルを遥か雲の下に大きく突き放した。 その後も歌では、武部聡志をはじめ、谷山浩子、銀色夏生、崎谷健次郎、飯島真理、原由子、MAYUMIなど、次々と彼女の元に個性的で彼女にあった鋭才が集まって高品質の作品をリリース。 その勢いはとどまることなく、2年目の86年して紅白歌合戦の初出場とさらに司会まで引き受けることとなる。 アイドルとして早くも頂点を極めた彼女は、翌87年から本人と事務所の意向によってか、女優の仕事へと大きく傾斜――この年は2本の映画を主演し、舞台「レ・ミゼラブル」を経験。音楽活動は彼女の自己表現の場と言う色を強めていく。アルバムのプロデューサーに自身が名を連ねるのはこの年のアルバム『ripple』からである。 彼女はセカンドアルバムの「ガラスの鼓動」以降、相当数の詞作をこなすが、それは提供を受けた谷山浩子や田口俊、松本隆などの詞作と比べても見劣りすることのない、高水準なものであった。「いちご水のグラス」「今だけの真実」「眠り姫」「アクリル色の微笑み」などアイドルポップスとして一流の詞作といっていいんじゃないかな。 途中「夢の中へ」という大ヒットも生まれるが、彼女とそのスタッフは座標が一切ぶれることなく、「彼女の自己実現の場としての音楽活動」をつづけていく。 (――帯のゴールデンタイムで、かつ自身の主演のドラマの主題歌となりながらシングルカットをしなかった(「Lucky Dragon」)と言うのも彼女ぐらいではなかろうか)。 歌は自己プロデュースの果てに末期は「Love」「moi」など自身のスキャンダルや私生活が透けて見えるような痛々しい作品が多くなったが、全体としてみると、無駄のない綺麗な流れで音楽活動を行なっていたような感じ。 どのアルバムも一定の方向性と水準を保っている。 歌手としての基礎力はあまり高いとはいえなかったが、鈴の音のような艶々として可愛らしい高音は魅力的で、特に後期の作品になると、そこに咲き零れる直前の花のような色香の強い妖しげな雰囲気が漂い、なんともいえない。 私は彼女の作詞した歌と彼女の声質がなんとも気に入っている。今でも彼女の新しい歌が聞きたいと思っている。彼女の憧れの先輩の谷山浩子のように、ぽつりつぽつりとでいいから"今の自分"を歌にしてほしいな。 ◆ AXIA (85.06.21/第3位/28.7万枚) 「青春という名のラーメン」のCFに象徴される斉藤由貴の少女らしい可愛らしさと翳りのコントラストを表現した盤といえるかもしれない。暗い曲と明るい曲が交互にといった感じで収められている。ただ、どちらサイドの歌もなんとも内向的なのが彼女らしい。 ただ「フィナーレの風」「感傷ロマンス」といったちょっと後のイメージと違う楽曲も入っていたりして、このあたりは模索中のファーストならではという感じがある。 「上級生」の"もしも偶然すれ違っていなければ 束ねたこの髪 ほどいていないでしょう"の年齢に似合わず妙に艶めいた表現力、タイトル作「AXIA」の"ごめんね 今まで黙っていて ホントは彼がいたことを"のあざとい女性心理を舌っ足らずでロリっぽく歌いこなすあたりに彼女の魔性の美少女っぷりが垣間見える。 後のスキャンダル女優っぷりも納得。 ともあれこのアルバムは、デビュー曲の「卒業」とそのカップリングの「青春」だけが段違い (――「青春」は高校球児の版「No Side」といったテイストで、これが受けないわけがないという。次のシングルにでもとっておけばよかったのに) 。その他の楽曲はその1ランク下という印象を受ける。 銀色夏生がCFの斉藤に惚れこみ、頼まれもせずにつくってプレゼントしたという「AXIA」、ユーミンの「Godd luck Good Bye」チックな来生姉弟作品の「雨のロードショー」も捨てがたいけれどもね。とはいえトータルクオリティーとしては以後のアルバムと比べるとちょっと落ちちゃうかなぁ。 ちなみにデイレクター長岡和弘、アレンジャー武部聡志というのはこの時点から既に彼女の音楽を語るに外せないメインの面子。6点。 ◆ ガラスの鼓動 (86.03.21/第1位/29.3万枚) このアルバムからいよいよ「斉藤由貴」のアルバムという感じ。斉藤由貴が4曲の作詞を担当 (内1曲はインストとそれをイメージした詩) 。さらに以後の彼女の作品に大きく影響を与える、谷山浩子、崎谷健次郎が作家として加わる。他、作家は松本隆、田口俊、筒美京平、亀井登志夫、MAYUMI、来生たかおと盤石。 「土曜日のタマネギ」はアカペラでの披露であるが、ここのコーラスの面子がなんとも豪華。斉藤をはじめ、谷山浩子、崎谷健次郎、亀井登志夫、久保田利伸、武部聡志、長岡和弘、というのだから凄い。「アカペラ」路線は後に「ripple」というミニアルバムへと結実する。 「今だけの真実」は彼女の長らくのフェイバリットナンバーで、ここでは谷山浩子のピアノ一本をパックに斉藤は歌唱している。郷愁を描かせたら右に出るもののない松本隆詞の「コスモス通信」や「情熱」もいいし、 斉藤の繊細な詞と、武部聡志の流麗な弦アレンジと、崎谷健次郎のハイトーンコーラスが完璧な「月野原」も秀作――アルバムタイトルはこの歌の"ガラスの鼓動 まだ見ぬ人 あなたにあげる"からだろうが、それにしてもいいタイトルだ。 シングル曲やB面が多く収録されていてオリジナルアルバムとしての美味しさには欠ける嫌いがあるけれども、や、いいアルバムですよ。これは。 アルバムが1つの世界観を作っている。漫研部長の少女趣味が高密度で結晶した名盤。 ちなみにこのアルバムが彼女の作品の最高売上。9点。 ◆ チャイム (86.10.21/第2位/26.7万枚) NHKの朝の連ドラ「はね駒」の高視聴率にアイドルとしての人気が絶頂であった頃のアルバム。前作を引き継ぎ、美事なまでの少女趣味の横綱相撲。 谷山浩子と競作になった「SORAMIMI」、崎谷健次郎がセルフカバーした「アクリル色の微笑み」、カルピスCFに使用された「予感」が収録。 「指輪物語」や「自転車に乗って」「悲しみよこんにちは」「青空のかけら」などは、後の彼女を知ってしまうとちょっと可愛らしすぎるかなと思えるけれども、当時の彼女の国民的アイドルぶりを思うと、欠かせないラインかな、と思ったり、ともあれ アイドルっぽいわかりやすい可愛らしさを出しつつも、そこに彼女の色もしっかりも出た作品といえる。楽曲のバラエティーと大衆性ではこのアルバムが1番かもしれない。 「ストローハットの夏想い」や「つけなかった嘘」「水の春」あたりも磐石だが、ファンとしてはやっぱり自作詞の「いちご水のグラス」 (――谷山浩子の作詞の「ひまわり」が用意されていたところ、彼女がこっそり詞を自作して無理やり嵌めてしまったという)、「予感」(――斉藤曰く"東横線"をイメージした詩。ディレクターに詞を見せずに"まぁ、いいから"と無理やりブースに入って歌っちゃったんだとか) 「アクリル色の微笑み」「あなたの声を聞いた夜」あたりに特にぐっとくる。 彼女の作詞は、ほとんど玄人はだしだ。これもまた捨て曲ナシの名盤。8点。 ◆ 風夢 (87.04.21/第1位/21.3万枚) 「ガラスの鼓動」「チャイム」「風夢」は初期三部作という感じ。同じテイストで作られ、どちらと甲乙つけがたいほどの高クオリティーだけれども、わたしはその中で、このアルバムこそベストと薦したいなあ。「チャイム」と比べると各曲のキャッチの強さはないんだけれども、それぞれの曲の流れに調和が取れていて、1枚アルバムを聞いた時の印象が最も強い。全体の完成度が1番高いのではないか、と。 ヒットシングルの「砂の城」や「MAY」も"シングルです"という押し出しの強さがなくって、アルバムの他の楽曲にほどよく溶けこんでいる。 特に「ひまわり」以降の後半の流れは完璧。 前作からのリサイクルが思わずはまってしまった谷山詞の「ひまわり」 (――ロマンチックな情景にどろどろとした三角関係を透明に描いた詞が秀逸) 、 溝口肇の軽やかなチェロの音に夕暮れの雑踏を背景にした小さなドラマを描いた「街角のスナップ」、飯島真理の作曲とコーラスに斉藤のミスティクな自作詞、金子飛鳥のバイオリンが切ない「眠り姫」、重厚なパイプオルガンの音色に宗教色すら感じる「風・夢・天使」など。アコギのやさしい音色に家族の暖かみを歌った「家族の食卓」(――彼女のトーク番組「斉藤さんちのお客さま」のテーマにもなった)、はファンには忘れがたい名曲。 他、オーソドックスな弦楽に文化祭を歌った「体育館は踊る」、仲直りの電話のつもりが突然親知らずが痛みだして、二人の会話は噛み合わず関係は修復不可能に、という「親知らずが痛んだ日」あたりも可愛らしいなあ。 とにかくよく出来たアルバム。 南野陽子「VERGINAL」や銀色夏生presents「バランス」などと共に80年代アイドルポップスの極北たる作品といっていいんじゃないかな。男性にとって"かくあって欲しい"という少女像と、女性にとって"かくありたい"という少女像がこれらのアルバムではぴったり重なっている。ここで表現されているのはまさしく"夢の少女"である。9点。 ◆ ripple (87.09.21/第5位/8.4万枚)
全作斉藤由貴の作詞によるアカペラ・ミニアルバム。CDのみの企画盤なので、前後の作品と比べて売上が大きく下回っている。 ちなみにこのアルバムで、はじめてプロデューサーに彼女の名前がクレジットされている。 それにしても改めて斉藤由貴の詞の舞台設定と、物語運び方のうまさに驚く。アイドルの詞としては減点するところがまったくない。他のアイドルにも書いて欲しいよ、と思うことしきり。 カルピスCFに使われた「うしろの正面だあれ」なんて、曲中のストップタイムが上手く詞の世界とリンクしていて、可愛らしいことこの上ない。 他、夏休みのバイト代全部費やして買った原チャリが嬉しくって、いつもの近所を走り回るという「Scooter 17」、夏祭りに思わずハイテンションになって憧れの先輩にヘンな姿を見られてヤベっという「ぴいひゃら」、好きな人とふたりきり気球船にのる夢に、これは夢よね、と思いながら、夢だからなんでも出来るわ、と迫っちゃう「冒険小僧」などなど。 ラスト「あまのじゃく」はアルバムタイトルからか海辺のさざなみのSEが聞こえてエンド。 小さいながらもこれまた濃密な世界を持ったアルバム。ちなみにコーラスは崎谷健次郎や木戸泰弘、比山清あたりはなんとか確認できるが、他誰が関わっているんでしょうか ? 7点。 ◆ PANT (88.03.21/第4位/14.5万枚) 88年はシングルリリースが自身の主演映画「優駿」の主題歌「ORACION 〜祈り〜」のみ。他の85年デビューアイドルたちがアイドルとしてそれぞれの頂点を極めようとしていた頃、一方の斉藤由貴は早くもアイドル歌手としてはほとんど勇退という位置にいく。 この作品は前作に続いて斉藤自身がプロデュース、詞も10曲中7曲を担当している。 原由子が後にセルフカバーした「少女時代」、アイドルとしての自身を戯画化した「かわいいあたし」、成人式に昔のクラスメートが集まって、という「振袖にピースサイン」あたりのもいいが、「夜のブランコ」のその後といった感じの、谷山作詞の道ならぬ恋のさりげない終わりを歌った「ブルーサブマリン」 (――後に谷山もセルフカバーしている) 、 ため息がぽつりぽつりこぼれるような儚く歌う「終わりの気配」といったあたりは、晩秋、枯れ枝に悲しみがまとわりつくがごとく切ない。内省的で暗示的な詞に、弦(――シンセか?)の荘厳なオーケストレーションが美しい「morn」、海原をたゆたうようなオケに失われた恋の物語がバラバラと展開していく「3年目」あたりも儚く美しい。 この時期の斉藤の本領が発揮されている良作。後の「Love」や「moi」の世界の前兆もまた、感じられる。 <アイドルなのにここまで自己を開示しちゃっていいの ? >という危うくも切ない恋の世界。このときの彼女はきっと恋をしていて、そして孤独だったんだろうなぁ、とぼんやりと思う。7点。 ◆ TO YOU (88.12.07/第12位/7.6万枚) クリスマスの企画アルバム。タイトルは全て"5W1H"で統一、アレンジもより荘厳で神々しく冷えた感じに統一、ジャケットは箱入りのブックスタイルとなっている。 また他のアルバムよりも気持ちリバーブが深めに作られているせいか、これまた不思議な空気感のあるアルバムになっている。ふわふわとしてとらえどころのない、降ってはすぐに消える淡雪のような、という感じ。 1曲だけ斉藤自身の作詞「Where 〜金色の夜〜」というのがあるがこれだけ異次元。「はじめから私は 嘘つき 偽善者 あなたを愛するつもりなどなかった」とか「切り裂かれて血を流す 恋がただ したかった」って、斉藤さんあなたクリスチャンじゃなかったっけ?ゴスで反キリストの匂いがプンプン。蜜蝋がとろとろ溶けるように妖しく、恋に身も心も濡れています。 他、給食のニンジンが食べれなくて居残りされてという可愛らしい「How come? 〜どうしてこうなの〜」、 いかにも"氷点下"という冴え冴えしたピアノの音色に、斉藤の鈴の音のような高音が楽しめる「Who」など。あと英語詞の曲が2曲ほどありますが、まあ、私にはよくわかりませんです。あ、でもマーチ調の「Why」は結構好きかも。7点。 ◆ age 〜アージュ〜 (89.04.21/第4位/13.6万枚) 武部聡志が勇退して、それまでサブ的役割であった崎谷健次郎がこのアルバムでは音楽監督に就任。詞も1曲を除いて谷山浩子の作詞で、久しぶりに斉藤由貴は歌手に専念している。 アルバムテーマは「ハウス」。まさしくハウスど真ん中の「In My House」なんて曲も収録されているが、ズブのハウス・サウンドはほかに「ガラスの天球儀」「N'ouble pas Mai」くらいで、さほど多くない。 谷山浩子は「ハウス」をそのまま「お家」としゃれで解釈したのか、「In My House」「Doll House」などといったタイトルのものがあるが、その遊び心がいい形で作用している。「In My House」はどこまでいってもどの扉を開けても鏡写しのように自分の家から抜け出せないといった感じで陽気に不気味だし、「Doll House」は恋人の腕の中で別れの予感を感じる少女の歌のように見えて<人形のまま無限のループに迷いこんでしまえたら>の部分にぞくっとする。この部分から、動かない人形同士の恋の妖しい歌とも聞こえる。 詞はどれもこれも内にこもって外から閉ざされていて、それでいて安らか、というよくよくみるとまさしく「おうち」な感じ。「ガラスの天球儀」も舞台は「天球儀」だし、「永遠のたそがれ」は"たそがれに時は止まり もう二度と夜はこない"と時間軸を外れ閉じてしまっているし、「雨色時計店」も今の時間がいつだかわからない時間軸がぐちゃぐちゃの小さな閉じられた世界。この谷山の独自の解釈がただのハウスサウンドに終わらない深みを作品に与えている。 同時期、今作のサウンドプロデューサーの崎谷健次郎は、自身の作品でもハウスサウンドを大胆導入したアルバム「KISS OF LIFE」を制作しているが、斉藤のほうが1枚上手といった感じかな。うちにこもった繊細で華やかであぶなっかしい少女趣味の世界。 このアルバムと同時発売のシングル「夢の中へ」が大ヒットするが、ヒットに流されることなくこの後もまったりと活動。ちなみに「Doll House」「LUNA」は谷山浩子がセルフカバーしている。7点。 ◆ MOON (90.07.11/第8位/8.5万枚) 斉藤由貴が企画を持ちんでつくったというまさしく完全セルフプロデュースのコンセプトアルバム。アルバム全体のテーマを決め、各曲ごとにコンセプトシートを制作して、そしてそれぞれに発注をかけて、仕上がった音源にその通りに斉藤由貴が詞を嵌めて、と作られたという。 今回の音楽監督はチャクラの板倉文が担当。 多元宇宙のように10曲の中に10個の夢があって、それぞれの脈絡のない夢の扉を斉藤由貴がひらいてはのぞきこみ歌にしていく、というアルバムになっている。精緻で透明で歪んだガラス細工のような過剰な作りこみは谷山浩子のコンセプトアルバム(――「歪んだ王国」など)に近い。 工業的な機械音、海辺の工業地帯の夕暮れの風景に人の営みを見る「永遠」(――斉藤の地元の京浜工業地帯あたりがモチーフか)。大正時代の銀座のモガの哀愁を陽気に歌った「大正イカレポンチ娘」(――バタ臭いジャズの音色が懐かしい)。「夢二と中原順一と高野文子の世界」と本人の語るぽかぽかと長閑な「少女が春の縁側で」。夜の移動遊園地をうたった「回転木馬」。性の高揚の後の虚脱のような白溶として妖しい「MA HI RU (瞬間)」(――本人はイメージとしては自殺に近いといっている。自殺というより、情死でしょ、これは)。かように万華鏡を覗き見るように夢の世界がうつろっていく。 ベストは「迷宮」。ダリやマグリット、ルソーの世界を目指したと本人はいっているが、いい線いっています。こういうゴスで爛れたムードを当時の彼女は求めていた節があって、それが上手い形で1つの作品になっているように見える。サビのボーカルが追いかけあう部分は果実が腐って溶けるような感じすらも、といった褒め過ぎか。 ラスト「ENDING 〜Hello Dolly〜」の種明かしのような幕引きをもって、このアルバムは終了(―――"人生なんてひょんなはずみだから 恋は軽やかに 夢はしたたかに 嘘は清らかに"という部分は好きだなぁ)。斉藤とリスナーはそこで夢から醒める。 おまけはひとり芝居「岡本さんの毎朝」。斉藤さんのいつもの日常の世界という感じ。ここで現実世界に引き戻されるという作りなのだが、これもまた微笑ましい。 実に斉藤由貴らしい、作りこんだアルバム。よく出来ております。この路線でポスト谷山浩子ってのも充分狙えます。ってそんなマイナーな路線を狙っても仕方ないか。8点。 ◆ LOVE (91.12.04/第16位/4.0万枚) アルバム制作前に彼女は尾崎豊との不倫スキャンダルを味わっている。その影響がこのアルバムには濃厚に漂っている。 前作とはうってかわって、生身のそのままの自分を表現しよう、と作られたアルバム。淡々として平凡過ぎるくらいの普通のメロディーでありながら、その奥にはっとするほどの切なさや悲しさが感じられるそういう作品、オケも必要最小限で必要な音だけにしようと斉藤が持ちかけて出来あがった作品 ――斉藤は以上のような今回のコンセプトを会議で話し合っている時、何か思いの溢れることがあったのか、説明しながらその場でぽろぽろと涙をこぼしてしまったらしい。 というわけで、ここで表現される"生身の自分"というのは、そんじょそこらの"生身"ではない。 精神の高揚の一瞬の沸点で作ったようなはりつめた作りになっている。 ピアノと弦の音が中心の、余分なものを配したオーケストレーションに、彼女の研ぎ澄まされた言葉が重なる。それはさながらひとり芝居か、シャンソンのよう。 一瞬目を離せば砕け散ってしまうような、そんなぎりぎりのスリルの世界。 朝の恋人との些細な会話をそのまま歌にしてしまった「朝の風景」は、ほとんどエディット・ピアフかという感じ。さりげなく話すように歌がこぼれて、それでいて生々しく真に迫っている。 さらに、自身を確認するかのように重々しく"なにもかも"を連呼する「このまま」の張りつめた美しさ(――「世界は終わろうとしている なのに 僕らは別々の家に帰る」の部分も凄い)。 電車が通り過ぎ、遮断機の向こうにいたあなたが消えて最後のさよなら、という「誰のせいでもない」は、"何もかも話すのがいいとは限らない"とか"あなたはなんにもわかっていない"とか"これきり逢わないこと知ってて、どうして私は笑っているの"とか色んな小理屈が頭の中でぐるぐるするも、最後の最後「ごめんなさい 愛しています 今でも」と吐露するあたりに背筋が凍る。 男との退屈なドライブに女の本音と建前が垣間見える「Julia」も秀逸(――間奏の食器の鳴る音と耳をくすぐるような斉藤のチャットも効果的。食事の最中の親しい女性たちの間だけの"ここだけの恋愛話"という感じがよく出ている)。 ラストは崎谷健次郎に提供した「意味」。シノワズリなメロディーライン、三柴理のピアノのみをバックに、自己の内面にドロドロとわきあがる情念を浄化せんとばかりに朗々と清新に、天からの声かといわんばかりに斉藤は歌いあげる。 かように完成度は確かに高く、これ以上でもこれ以下でもないというワンアンドオンリーの作品なのだが、 一方で業の深い女優の日記を見せつけられているような、なぜ俺はこの人のトラウマにつきあわされているのだ、という気分にもなる。傑作には間違いないが、ドキュメンタリ―の息苦しさが全体に漂っている。これを認めるかどうかというのは一種の踏絵に近い。 ちなみに今回の音楽監督は上杉洋史。いい仕事しています。雪解け水のように澄んだ音。10点。 ◆ moi (94.12.07/第76位/0.6万枚) 結婚直後、デビュー10周年直前にリリースされた現在のところラストアルバム。"因業女優の人生の着地点アルバム"といったら失礼ないい方になるだろうか。 今回はテーマを決めずに作ったと本人は当時のインタビューで語っていたが、ほとんど「Love」の後日談といった作りの作品に仕上がっている。失った恋への悔恨、諦念、そして新たな出会いに揺れる心。彼女の書く詞はこの時期の斉藤由貴の魂の歴史そのまんまといって過言でない。同時期に上梓した斉藤由貴の小説「NOISY」と同じ、この時期の彼女そのものの作品である。 ちなみに半分が洋楽カバーで、半分が斉藤由貴作詞、筒美京平作曲。アレンジは前作からの上杉洋史と、澤近泰輔が担当となっている。 すべてのはじまりであったバートバカラック「The April Fools」の日本語詞は斉藤の手によるものだが、"瞬間に恋をした あなたの眼差しにすべてを見た"とこれは露骨に道ならぬ恋を歌っている。(――ちなみに斉藤由貴の小説かエッセイかに愛する男と「The April Fools」を聞くという一節があったと記憶している。あれはどの作品だったか……)。 さらに夕暮れ時、過ぎた恋を振りかえっては、様々な後悔の念にさいなまれ迷子のような気持ちになる自身を歌った「夕暮れ日記」、 "なぜ あなたは私のことをさけるほど嫌いになったのか まだわからないの"と直球でつぶやく「なぜ」(――この曲はちょうど「卒業」とリンクした作品ではなかろうか。筒美京平作曲で、ラストシングル。2番の詞のプラットホームでの情景を見るに、どうも斉藤は意識して詞作したのではと思えて仕方ない)、 "他人の目 塀をめぐらせ ウソの家 作っては また壊し"と歌う「答える声はなくても」(―――「私を助けてと 助けてと 呼ぶ」の部分もかなり怖いッス)もまたあまりにも直球過ぎる。 それら過剰な"そのままの自分"の世界の合間に、やわらかく懐かしい洋楽ナンバー置いて、アルバム全体を均衡に保っているという感じ。斉藤由貴は歌手としての基礎力というのはないけれども、この頃になると声の可愛らしさにプラスなんとも艶っぽいいいムードが出てきて、ここの洋楽ナンバーなんかも結構いけたりする。 鼻歌っぽくさりげなく歌うとなんとも耳がくすぐったいような感じがして心地いい。「You Light Up My Life」のように歌い上げちゃうとちょっとアレだけれどもね。 そしてラストは「あなたと出逢って」。 あなたと出逢ってココロのコオリが ゆっくり溶けてゆくのがわかる この歌で斉藤は今までの恋と今までの傷をすべて昇華している (――この曲の歌入れの時もちろんという感じで、斉藤由貴は泣いている) 。 このアルバムリリース直前、斉藤由貴が結婚、そしてラストの曲がこれとはあまりにも出来すぎていて、あまりにも嘘がなさ過ぎる。 とはいえ、そんな馬鹿正直なところが斉藤由貴らしくっていいかな、と私は思う。 そしてエンドロールのように「The April Fools」の英語詞版が最後の最後に流れて、アルバムは幕。斉藤由貴の歌手活動もここで一応の終了となる。9点。 ◆ Vintage BEST (08.06.18) 07年以降、にわかに歌手活動を再開した斉藤由貴の新作ベスト。意外な収穫。これ、いいわ。前年末リリースされた「悲しみよこんにちは 21世紀バージョン」をさらに発展させたベスト盤であり、セルフカバーであり、ニューアルバムという感じ。 91年末にWOWOWで放送された擬似ライブ「聖夜」の音源(サウンドプロデュースは斉藤ネコ)、昨年のセルフカバーの音源(サウンドプロデュースは澤近泰輔)、さらに20年以上前のオリジナル音源(サウンドプロデュースは武部聡志、上杉洋史)、それら様々な出自の音源を絶妙にミクスチャーして、さらに、そこにアルバム用の新しいサウンドを加味させて、再編曲、再編集して、ひとつのアルバムにしあげた、というかなりトリッキーなアルバムなんだけれども、まぎれもなく「斉藤由貴」のアルバムであり「今」のアルバムであるのが、嬉しい。 カバーとかリアレンジって、元のイメージをこわして残念な作りになりやすいんだけれども、きちんと以前の良さを残している。 それでいて今の時代に合わせてリファインさせていて、音がまったく古びていない。20年以上前の音を使用しているとはとても思えないのだ。 聞いて、オリジナルのほうが良かったと落胆するようなこともないし、オリジナルが途端に色褪せるということもない。 制作スタッフに、彼女の作品に対する深い愛情と理解を感じずにはいられない。――というのも当たり前の話で、このアルバムプロデュースは、斉藤由貴のデビュー以来の音楽プロデュースの全権を担っていた長岡和弘、リアレンジは斉藤の歌手活動後期のアレンジャーであった(中森明菜ファンにはおなじみ)上杉洋史が担当しているのだ。 斉藤由貴って、つくづく理解者に恵まれているよなぁ。8点。 ≫≫≫≫≫斉藤由貴・全シングルレビュー へ
|