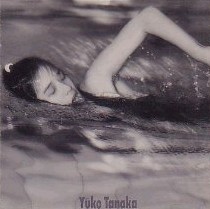◆ JULIE 7 The3rd 沢田研二リサイタル ◆ Mis Cast ◆ 田中裕子 「泳いでる……」 ◆ マチベン ◆ 75年、ひとつの蹉跌 ◆ ジュリーのドームライブを知る ◆ 沢田研二 「SONGS」
久世光彦をさくら色のやおい妄想で萌え萌えにさせた (――詳しくは久世光彦著「ひと恋しくて」 参照)、内田裕也とのデュエット「トラブル」など、ライブを完全収録。ほか「Get back」「Move over」「Johnny B Goode」「Cotton Fields」「The Jean Genie」と洋楽カバーを中心に構成されている。昔の歌謡曲系のライブアルバムって、大抵こうだよね。何故か洋楽カバーメイン。 なんてったって、このアルバムの魅力は若ジュリーの受け臭さ(笑) につきるかと。「裕也さん、いくつになったのよぉ」のジュリーの口ぶりとかっっ、かなりエロいよっっ。ええいっ、おれも「まよてん」書くっっ、そう思ってしまうことうけあい。内田裕也、久世光彦をはじめ、樹木希林、安井かずみ、渡辺美佐などなど、数多くの年上の男女の心をとろかした年上キラー・ジュリーの魅力が満載のアルバムとなっております。 てか、あの内田裕也が照れまくり、「やりにくいなぁ」とこぼしてしまう、やに下がって可愛いおじさん化してしまうんですよっっ。こんなとこ、ジュリーでなければありえませんてば。 時期的には「危険なふたり」の大ヒットで、この年日本歌謡大賞を受賞、ソロとしては第一期黄金期にまさしく差し掛かったというところ。声も乗っていて、ジュリーの歌手としての自信も漲り、タイガース時代のジュリーにはなかった確信犯的なエロさを周囲に振りまいております。あぁ、映像で、これ、見てぇっ。 (記・07.06.25)
たしかにこのアルバムの井上陽水、本気指数高すぎ。同時期の陽水のアルバム「ライオンとペリカン」も、陽水のオリジナルアルバムでトップクラスのクオリティーだけれども、それと勝るとも劣らず、密度の濃い詞・曲が並んでいる。捨て曲なんて、あるはずがありません。 しかも、それをムーンライダーズの白井良明がニューウェーブ全開の編曲しているわけで、もう、傑作にならないはずがないじゃないですかっ。沢田研二×井上陽水×白井良明。まさしく「ミス・キャスト」な三人の、しかし、だからこそ生まれたこの緊張感。三者の才能が、スパークしております。ピコピコ打ち込みの「Darling」、ビックバンドがかなり無茶している「次のデイト」、なぜか唐突にヨーデルな「How many "Good-Bye"」、「ジャストフィット」は今でもライブに欠かせない名曲。アルバム全体に奇妙な危うさが漂っているのがこのアルバムの特徴。陽気な絶望というか、徹夜明けのような変な高揚感。テンション高いんだけれども、どこか閉塞している。 沢田研二は『TOKIO』で井上バンドと決別して以降、音楽的に過激な進化を遂げていくのだけれども、このアルバムと次作『女たちよ』は、その極北なんじゃないかな。沢田の実験性が過激に露出した作品がこの二枚かな、と思う。セールスも「勝手にしやがれ」直後にリリースした「思い切り気障な人生」に次ぐ成績を残しております。 (記・07.03.27)
当時不倫まっただなかの沢田研二と、当時の沢田の個人事務所社長・大輪茂雄がプロデュースしている。 作家は、沢田研二、佐藤隆、BORO、松本一起、湯川れい子、全編曲を深町純が担当。 なわけで、「架空のオペラ」〜「Co-colo」時代のジュリーそのまんまの異国情緒路線のアルバムなんだけれども……、これってそのまんまジュリーが歌ったほうがいいような……。 ってか、これ、露骨にオーバープロデュースだよな。 田中裕子の歌唱も、愛と女優魂でなんとか乗り切っているというところで、彼女の歌う必然というのは、ひとまずあまり感じられないし、どこまでも余技そのものという感じ。 また、よくある「女優の歌」的な色気も、さほど感じないんだよね。 ジュリーが、あまり深く考えずに今の自分が好きな歌、自分の歌いたい歌を目の前に持ってくるのを「あ、沢田さん、こういうのが好きなんですね」って感じで、裕子さんは恋人の思うにあわせて歌っている、という、そんなアルバムか、と。 曲自体は、いいもの多いんだけれどもなぁ。 当時の女性歌手だったら、明菜サマとか高橋真梨子とか、そのあたりのラインの歌手が歌ったほうが……って、失礼? ま、ジュリーがプロデュースしたかったんだ。仕方ないとしか、いいようがないわな。 惚れた女に、あっほあほにこわれるジュリーも、わるくないです。――って、結局そういう楽しみ方ですよ、わたしは。 (記・06.06.01)
◆ マチベン NHKをぽっとつけると、初老のどっからどみてもおじぃちゃんです、本当にありがとうございます、な沢田研二が出ていた。あ、これが「マチベン」ね。 まもなくすると、岸辺一徳も、出てきた。不治の病に陥り安楽死したいという一徳の依頼に、渋く活躍する沢田。沢田と一徳の間には、それまでの人生でいろいろあった模様ながらも、男の腐れ縁的友情というか、そういうノリで話は進み――、というどっから見てもタイガースファンあわせな回でした。 しかし一徳、あいかわらず馬鹿みたいに演技が上手いな。沢田も決して演技は下手ではないけれども、一徳の上手さに完全にくわれとる。 ちなみに今の沢田研二は、沢田研二であって、ジュリーではないので、そこんところひとつ、よろしく。 (記・06.04.30)
◆ 75年、ひとつの蹉跌 沢田研二で好きなエピソード。 75年に二度の暴力事件を起こして、ジュリーは自主的に一ヶ月間すべての仕事をキャンセルして謹慎をすることにしたのだけれども、その間、なにをするのでもなく、ずうっと家にこもってテレビの歌番組を見ていたのだそうだ。 当時は歌番組全盛、テレビのチャンネルを変えればどこかで誰かは歌っていた。ガチャガチャとせわしなくチャンネルを変えながらほんの数日前まで自分が出ていたはずの番組をじっと、食い入るように見つめる。 華やかな世界、しかし自分はそこにいない。もちろん面白くない。けれども見るのをやめることができない。 しかし、見つづけているうちに、沢田研二の中で、テレビに出ること、歌うこと、という意味が少しずつ変わっていった。 かつてのGSの王子様・ジュリーはこの時死に、女装も辞さない過激なコスチュームを新曲毎にとっかえひっかえし、「一等賞」獲得を宣言するにまったく億さない、「わしは見世物や」と言い切る、あのジュリーが、このとき生まれた。 「勝手にしやがれ」「憎みきれないろくでなし」「サムライ」「ダーリング」「カサブランカダンディー」「TOKIO」と彼の代表曲が連発するのは、それからすぐのことである。 それは真の全盛期を迎えるためにあったひとつの蹉跌であった。 (記・08.07.16)
◆ ジュリーのドームライブを知る ジュリーが東京ドームと大阪ドームでコンサートをやるらしい。 今年に入ってそんな噂をちらほら聞いていたが、まさか、あの沢田研二のことだとは思わなかった。やるらしい。しかも五時間半の公演。もちろんドームライブ史上最高齢。 球場コンサートは「TOKIO」リリースの頃の、つまりは全盛期の横浜スタジアム以来。――という。 無茶だ。 今でも毎年コンサートツアーをしていること、ニューアルバムも毎年出していること。それを知っているのは熱狂的なファンだけだというのに。でもそんな無茶をする沢田研二が私は結構好きだ。 http://julieindome.jp/ 昨日、おじいちゃんになってしまったジュリーが「ブロードキャスター」でちろっと映っていたけれども、やっぱりちょっと切なかった。 彼の今の歌は「おじいちゃんのラブソング」以外のなにものでもない。僕はまだおじいちゃんではないから、そこが少しばかりつらく、かなしい。 でもそれはデビュー以来、たえず「今」を表現していた沢田研二なのだから、当然のことなのだ。 生きるというのは、生きつづけると言うのは、変わっていく自分や周りを受け入れること。 こんな大きなイベントをやっても、老醜、とか、昔はきれいだったのに、とか、そんなことばかり云われるのは沢田本人が一番よくわかっているだろう。 それでも自分をストリップしてしまうのが、スターの証なんだと僕は思う。 なにがなんでも生きるということ、そしてその過程を大衆に晒すということ、それがひとつの物語となるということ。 失敗でも成功でも、いい。ドームには、行こう。 (記・08.06.29)
◆ 沢田研二 「SONGS」 7年ぶりのテレビ歌唱。沢田研二の「SONGS」第一回を見る。 まぎれもなくおじぃちゃんなんだけれども、やっぱり沢田研二なのだ。 新曲中心の構成に「ナツメロ歌いにはならない」という気骨もあいかわらず。 2001年からキーボード抜きのサウンドになって、しばらく彼の新曲を聞く事がなくなっていたのだけれども、いつのまにやらキーボードも復活していて、うん、良かった。 「ROCK'N ROLL MARCH」の熱さは相変わらずだし、「わが窮状」のラブアンドピースぶりも相変わらず。「窮状」とは「今の日本の窮状」であり「第9条」でもある。 苦しい今だからこそ、大切なこの9条守っていこう、という憲法第9条の直球讃歌というのも、凄いな。この年齢だからこそ衒いもなく出来るのかな、という感じがする。 タイトルの駄洒落は「湯屋さん」→「(内田)裕也さん」「Rock 黄 Wind」→「六甲おろし」とこれまたいつものジュリー。 つまりジュリーはジュリーなのだ、ということを再認識したのであった。ニューアルバムもまた聴いてみようかな。 (記・08.09.30)
|