小説 単発小レビュー集
◆ 瀬戸内寂聴(ぱーぷる) 「あしたの虹」 ◆ 江森備 「王の眼」 ◆ 須和雪里 「サミア」 ◆ 中井英夫 「人形たちの夜」 ◆ 夏目漱石 「夢十夜」 ◆ 久世光彦 「桃」 ◆ 皆川博子 「蝶」 ◆ 赤江瀑 「遠臣たちの翼」 ◆ 栗本薫 「JUNE全集」 ◆ 紫宮葵 「とおの眠りのみなめさめ」 ◆ 紫宮葵 「黄金のしらべ 蜜の音」 ◆ 榊原史保美 「蛇神 ジュナ」 ◆ 榊原史保美 「ペルソナ」 ◆ 嶽本野ばら 「デウスの棄て児」 ◆ 嶽本野ばら 「エミリー」 ◆ 梨木香歩 「西の魔女が死んだ」 ◆ 穂村弘 「手紙魔まみ、夏の引越し(ウサギ連れ)」 ◆ 松尾スズキ 「クワイエットルームへようこそ」 ◆ 佐々木丸美 「沙霧秘話」 ◆ 恩田陸 「puzzle」 ◆ 梅棹忠夫 『文明の生態史観』 ◆ 筒井康隆 「馬の首風雲録」 ◆ 筒井康隆「美藝公」 ◆ 杉本苑子 「今昔物語ふぁんたじあ」正・続 ◆ 酒井政利・北島由記子「パラサイト」 ◆ 唐沢俊一 「トンデモ美少年の世界」 ◆ 大塚英志+東浩紀 「リアルのゆくえ」 ◆ 「1946〜1999 売れたものアルバム」 ◆ 中江有里「結婚写真」 ◆ 田原俊彦 「職業=田原俊彦」 ◆ 佐藤明子 「沢田研二という生き方」 ◆ 銀色夏生 「テレビの中で光るもの」 ◆ 川瀬泰雄「プレイバック 制作ディレクター回想記 音楽「山口百恵」  ◆ 瀬戸内寂聴(ぱーぷる) 「あしたの虹」 (08.09.25/毎日新聞社)
◆ 瀬戸内寂聴(ぱーぷる) 「あしたの虹」 (08.09.25/毎日新聞社)寂聴さんが、ぱーぷるなる偽名をつかって御ん年86歳にしてケータイ小説に挑戦したらしい。 http://no-ichigo.jp/profile/show/member_id/73865 いきなりのプロフィールにのけぞり、すげぇすげぇ、ぱーぷる婆さん、貪欲すぎる、と喰らいついてみたけれども、読んでみたら、結構フツー。ケータイ小説というよりも、80年代のコバルト文庫という感じ。 改行しまくったり、センテンスを短くしたり、漢字をひらきまくったり、わざと間抜けな描写にしたり、こまかい所に努力が感じられるんだけれども、根本的なところでちゃんと文章がうまい。ちょっとした語彙や皮膚感覚のズレもあいまって、プロの、大人の文章というのがひしひしと感じられてしまう。「大人が作った子供向け」という感じなのだ。 まあ、確かに、源氏物語の昔より乙女のツボなんてものはさしたる変化もなく、大映ドラマも韓ドラも少女漫画もコバルトもBLもそしてケータイ小説ですらも、その物語の骨格だけを取り出せば大同小異の似たり寄ったりのラブストーリーだったりするわけだけで、女力のありあまった現役乙女な寂聴センセーも、ある面においては、ケータイ小説を書くことはできるのだろう。 しかしこの、溢れかえる微妙な感じというのはなんなのだろう。しばし考えて、はたとわかった。 「この小説、全然へぼんじゃないからだ」 古くは「影人たちの鎮魂歌」、あるいは「シャイニーマーメイド」。 超絶的に下手で、かつ、リアリティーゼロのありえない設定てんこもりの小説なのだが、作者の暴走する激しい愛とパトスと妄想につい読まされてしまう、むしろそのやり切った姿勢に読後に感動すらしてしまう、そんなへぼいけど愛に満ち溢れた物凄い作品を、敬意をこめて「へぼん」と女性同人界では呼ぶ。 「小説なんて今まで一度も書いたことがない、けれどもわたしはこれを書きたいんだ」 この無駄な愛と情熱と若気が奔流となって心の喫水線を溢れ出た時にへぼんは生まれる。つまり――、人が小説を書く人として生まれる時の「おぎゃー」という最初の一声、それが「へぼん」なのだ。 赤子の泣き声が伝わるように、へぼんは拙かろうと、その全身全霊をこめた一心さゆえに伝わるのだ。 しかし、赤子が成長していつか大人になるように、「へぼん」な作者もやがて、書きつづければ激しい熱は冷め、しだいに固まっていく。プロになる人もいれば、それなりだが上手くなった人、下手なりにまとまってしまう人、しかし赤子が赤子のままでいられないように「へぼん」のままでいられる人は、ほとんどいない。 よって完璧なる「へぼん」はその存在自体が一発屋であり、生まれたとたんに伝説となるのである。熱塊ような激しいパトスは「へぼん」だけの特権なのだ。 プロフェッショルな場でない同人界には、このような「へぼん」要素をもつ作品がたくさんある。むしろおのれのへぼんな作品と相手のへぼんな作品を叩きつけあい、ありあまった情熱と妄想をさらに増幅させていく、それが同人という場の本来のなのでは、とわたしは思っている。 それはケータイ小説という(本質的には)アマチュアリズムな場でも、同じではないのかなあ。 ケータイ小説を「下手だ、読むに耐えられない」と評するのは、どこか違うとわたしは思っている。あれは、言葉を持たないものが、言葉を持たない同志に向けて必死につたない物語を綴っている、その共犯関係で成立している世界なのだ。 であるから、このケータイ小説「あしたの虹」がもし評判になるとしても、それは本来ケータイ小説を楽しむ層とは別なんじゃないかなぁ、という気がする。言葉を武器として巧みに扱うプロで大人な瀬戸内寂聴だし、それは文章から滲み出ているもの。 ケータイ小説の読者層からは「子供同士で楽しく盛り上がって遊んでいるところに割りこんでくる悪気はないけど無粋な大人」といった感じで軽く受け流されるのではないか、と。 「見てくれはこんなだけれども、みんな混ぜてよっ。わたしだっては本当はみんなと一緒にお砂遊びや鬼ごっこがしたいのっっ。したくてしたくて仕方ないのっ」という感じのやむにやまれぬ熱いパトスは作品から感じなかったんだよね。ちょっと遊んでみよっかな、という軽い感じ。全然向こう見ずでもなければ、むちゃむちゃでもない。心に余裕のある作家のあくまで「お遊び」なのだ。 上手くてもいいけど(――ってこの言い方も凄いが)、その辺の本気汁出てるかいなか、どれくらい必死か、本当に仲間かどうか、といった峻別は、あの世界、厳しいよぅ。 こういう「気持ちは十代」なお年寄りや中年、わたしは嫌いじゃないですけどね。子供の世界に大人が本気で入りこむのは、なかなか難しいものです。 蛇足。創作をつづけていくうちに少しずつ失う情熱を同人屋はどうやって取り戻すのか。その時、彼女たちはジャンルを変えるのです。 つまり同人歴長めの人でジャンルはまりたての時の作品が完成度と情熱の掛け算した数値が一番高く、一番面白いぞ。と。 (記・2008.9.27)
 ◆ 江森備 「王の眼」 (全四巻/01.02〜04.12/角川書店)
◆ 江森備 「王の眼」 (全四巻/01.02〜04.12/角川書店)「天の華・地の風」で80年代のJUNE界を震撼させた江森備さんの新作は エジプト神話をモチーフにしたヒロイックJUNEファンタジー。 以前一巻の半分だけ読んで、うーん、古代エジプト、親しみのもてないテーマ――つか、固有名詞がわかりにくいんだよ、と、ずーーーっっと積読のままだったのを数日前、なんとはなしに手にとったのだけれども、お、おもろいやんけっ。 三巻途中まで読んだところだけども、いやあ、凄い。天華地風はもちろん、日処天や残神支配や薫や榊原などなど、重量級長編JUNEを味わっているような充実感。 たしかに、作品の舞台からして、ハードル高いんだけれども(――もう、きちっと歴史や宗教もろもろ調べあげて作品に溶け込ませてますからっ)、それをおしても、これはJUNESTとして読むべき一冊であるな。 いま、ふと思ったところを書きとめ。 ・敵方の宰相・ネフェルトゥムと国王・セティは、魏延・孔明的な共犯関係。自らが捕らえられながらもセティの命乞いをするネフェさんはかぎりなく江森三国志ラスト的。 ・主人公のハルの好感度の悪さは異常。思慮浅く、粗暴で、不遜で、怠惰で、好色で、視野が狭い。でも、これ、男性作家が書いたら、けっこう典型的な少年漫画ヒーローというか、普通に素敵な英雄になっちゃいそうでもある。本宮ひろし的キャラというか。 ・だから、江森さんはフェミニストなんだな。江森三国志でもそうだったように、ここでも男性社会的価値観の悪しき部分をねっちりと書き上げている。その腕力は物凄い。 ・だから「男性」に人としての誇りを踏み潰され、「女性」にされた過去のあるセティとネフェルトゥムはともに孔明ともいえるかも。作者自身の似姿なのかな、と私は感じてしまう。 ・関係ないが、贔屓キャラは、大人の度量と行動力を兼ね備えた(とっても魏延的な)武人イアンパパと、おバカなハルに絶望しながらもはなれることの出来ない(生まれもってのお世話キャラの)異母兄アンプたん。 ・やおい萌えなら、ネフェ・セティ・カームテフ・アアシェリの四角関係でっっ。寝技でカーフテフを篭絡するセティさんと、それを嫉妬するネフェさん(――中庭にささやかな家庭菜園作ってたり、鳩をいっぱい飼ってたりしてます、泣く子も黙る国家の頭脳なのにっっ、かわうぃ)、萌ゆるぅ。 ・結果的に二重スパイ的行動をとってセティを裏切ったカーフテフは、江森三国志で言えば姜維かな。でも二巻ラストで後追い的に自殺したのに、哀。 ・国家が少数の異民族に蚕食されて瓦解していく様が妙にリアル。平和ボケして相手の文化を理解しようとしない異邦人を懐に招き入れると、とんでもないことになるんだなぁ。 ・ハルとアンプの父であり、諸悪の根源、ウシル前王は、残神のグレッグに見えてきた。劣等感の強い田舎漢って、ろくなもんじゃないよね。その攻撃衝動、どうかしてるよ。 ・今回、文体がヒロイックファンタジーを書く時の(全盛期の)栗本薫にかなり近いのに、驚き。当時の薫からくだくだしさを三割減させて読みやすくさせた感じ。さすが小説道場最高位の門弟。いっそグイン・サーガ、江森さんが書けば……。 ――ってわけで、続き、読んできます。 (記・2008.12.6)
――というわけで、読み終えた――のだけれども、あまり今は言葉が出てこない。何をいっても陳腐な褒め言葉になりそうな気がする。素晴らしい。素晴らしい物語だ。欠けたるところは、なにもない。 15歳の頃、手塚治虫の「ブッダ」を読んだ。 「物語」を読んだ、と、はじめてその時おもった。良いことも悪いことも聖なるものも邪悪なるものも、素晴らしさも醜くさも、絶望と希望、祈りと嘆き、すべてがおさまっている。物語には、人として生きる、そのすべてがおさまっている。 こんなに素晴らしい表現があるのか。心揺さぶられ、畏れと憧れをはじめて感じた。小説や漫画、映画といった表現手段の差異は関係ない。物語を紡ぐというそのこと、――それを見、語ること。真実の眼で、あやまたず、たゆまず、語ること。それに15歳の私はひれふした。 それに近い感慨が、「王の眼」を読み終えた私をおそった。もし、JUNEという表現方法に嫌悪を持たないのであれば、是非読んで欲しい。 文章力、物語の構成がすばらしいのはもちろん。そこに描かれている宗教・歴史・民族・文化の咀嚼と理解力の確かさ、なにより人間考察の冷徹さと、それだけにとどまらない懐の深さ。 JUNEたる物語として「萌えながら」楽しめるのはもちろん、物語から様々な角度で学び、考うることもできる。そこに描かれているものは、ことは、人の世の普遍にある、感情であり、課題であるのだ。 彼女の前作「天の華・地の風」をはじめ、榊原史保美「風花の舞」「荊の冠」、萩尾望都「残酷な神が支配する」など、わたしにとって頂点たる、「永遠のJUNE作品」のなかに、新たにこの「王の眼」が、加わった。 拍手したい。誰に、というわけれでもないけれども。 ああ、それにしても、"青ハス"ネフェルトゥムくんの一途っぷりと、セティ様の汲めどもつきぬ魔性っぷりよ。 (記・2008.12.15)
 ◆ 須和雪里 「サミア」 (93.11/角川ルビー文庫)
◆ 須和雪里 「サミア」 (93.11/角川ルビー文庫)久しぶりにJuneを読んでみようと思った。小説道場門弟時代の須和作品。93年、角川ルビー文庫。初出はもちろん小説JUNE。 山奥で家族といっしょに暮らしている平凡な男子高校生の前に突然現れた金髪の超絶美青年、彼は自分をエイリアンだという、そして自分は彼にとって運命であるという――ってこれ絶対元ネタは「海のアリア」だよね。 エイリアンの美青年が、平凡な男子学生である主人公に物凄い勢いでアプローチしまくる、なんだ一体なに目的なんだ「いや、君の存在自体が僕の目的なんだよ」っていう。んでその目的をよくよく聞くとSF入ってます、っていう。と、そこまでは「海のアリア」だからいいとして、ラストの急展開、いきなり主人公がエイリアンの彼と寝た後に心中気分になるのがどうにもうすっぺらく感じた。 田舎暮らしのなにに不自由するも、なにに屈折するともない純朴で健全な少年がいきなり心中しようと決意するにはあまりにもリアリテイーが足りてないのだ。Juneだからラストはやっぱり心中だよね、というテンプレ臭が――といったら言い過ぎだろうか。 続けて収録作「影法師が泣いている」「暗珠」と読んだが、どうにも乗りきれない。 「影法師が泣いている」は、幽霊である「わたし」の、人をひとり殺し悪霊にまでさせながらも、最後までどこか他人事めいてて、きちんと相手と向かい合わないのにイライラとさせられたし、「暗珠」は逆に死ぬの生きるの愛してるの愛していないのの応酬ばかりでなんだかひどく息苦しく、また陳腐にも感じた。 そんな七面倒なことばかり考えてないでさ、好きな人を抱きしめればそれで終わりじゃない、なんでそれが出来ないの。 愛したいのに愛せない。それはこの世の中ままあることだけれども、その悲しさとおかしさをこれらの作品に感じたかというとそうではなかった、 それよりなにより、ここにある逡巡や臆病や保身が、今のわたしにはひどくつまらないものに感じる。 もう私はJuneを必要としていないのかなぁ。 例えばこれを、高校生の頃読んでいたら、私は感動していたのだろうか。よくわからない。 (記・2008.9.25)
 ◆ 中井英夫「人形たちの夜」 (76.04/潮出版社)
◆ 中井英夫「人形たちの夜」 (76.04/潮出版社)76年出版。連作長編。 生きとし生けるもののつましい営為は、不条理なる神の指先で簡単に崩壊する。 積みあげたもの、重ねつづけたものは無惨に打ち毀され、かわりに現れる茫漠とした新たな地平に私たちはただ呆然とするしかない。 何故私たちは理由なく苦しまなくてはならない、弄ばれなくてはならないのだ。 神の残酷な仕打ちにひとり立ち向かうのが中井英夫という作家である。 彼の小説それ自体が、作者の統御の行き届いた巧緻なる人工的なオブジェである理由がそこにある。 彼の人工なるもの、論理なるものヘの偏愛は、つまりは人類から神への挑戦状なのである。 しかし、人類は神に敗北を喫するように、中井英夫の描く物語もまた、太陽に向かったイカロスさながらに、最後の最後に失墜する。 彼は常なる敗北を宿命づけられた反逆児である。 この小説においても「わたし」の築きあげた精緻なる完全犯罪は、最後の最後の「貴腐」というたったひとつのキーワードのみによって瓦解する。 その瞬間、「わたし」は舞台から霧散し、幻の王国は崩壊する。 がらんどうの舞台の上には、先ほどまでヒトであったはずの人形たちが、虚ろな硝子玉の眼をして転がるばかりだ。 どのように食い止めようとも、月蝕領は崩壊し、流薔園は変幻する。 しかし、それでいいんじゃないかと、私は思う。 人という生き物もまた、どれだけ憎しみを積み重ねても、ひと雫の愛ですべてを蕩ろかされてしまう、不条理で非論理的な生き物なのだから。 彼の瞋恚なる怒り、憎しみ、あるいは透徹した美意識を、私は理解できるが、そのように生きることはできない。どうも根がだらしがないらしい。 アホすぎる蛇足。 第3部「秋」は、暗号解読"東北温泉めぐり"ミステリーツアーだったのだけれども、ホームズ役の主人公・裕とワトソン役の助手・宮下が、温泉宿でなんとなくいい雰囲気になって、いたしはじめたのにはビビった。 つか、萌えた。"二日目は、むしろ彼からむかい入れ、求めさえした"んですかっっ。 ……腐でごめん。 (記・2008.7.14)
 ◆ 夏目漱石「夢十夜」 (1908.8/)
◆ 夏目漱石「夢十夜」 (1908.8/)文豪としてあまりにも高名過ぎるので、今まであえて避けていたけれども、いいかげん思春期みたいな安い反骨はやめようよ、と、タイトルが素敵なこれを読んでみた。驚いた。夏目漱石って、こういうのも書く人だったんだ。 幻想小説?不条理小説? 「こんな夢を見た」という書き出しから、夢の不条理が断片としてそのまま10作と言う、だから「夢十夜」と。 何万匹もの豚が「私」の鼻を舐めるためだけに突進してくる第十夜(テーマ曲は「空からブタが降ってくる」だな)はナンセンスっぷりが素敵。 「百年、私の墓の傍に坐って待っていて下さい。きっと逢いに来ますから」といって事切れた妻を待ちつづける「わたし」を描いた第一夜、これは文章が磨きこまれてとにかく美麗、ほれぼれする。 ど直球ホラーな第三夜もなかなか。傑作です。 (記・2008.6.8)
 ◆ 久世光彦 「桃」 (00.02/新潮社)
◆ 久世光彦 「桃」 (00.02/新潮社)これが実に著者初の短編集、って、ええっ、そうなん? 「蝶とヒトラー」とか「恐い絵」とか「昭和幻燈館」って、エッセイという態を装った短編小説集だよね。 というわけで、久しぶりに久世光彦の趣味全開のあやし耽美の世界。 いまのきわで「陛下、陛下」と呟いた父のひみつ「尼港の桃」は、長編「陛下」の世界だし、廃墟に住む年老いた豆本作家と二匹の猫の暮らし(「囁きの猫」)は「聖なる春」路線、女語りの「いけない指」のこそばゆさは「謎の母」に通じるし、 足ぬけした遊女ふたりの粋で滑稽な偽遍路「同行二人」は彼の演出した「危険なふたり」や「自由な女神たち」のよう。 どれも好ましい作品ばかりだけれども、表題作「桃――お葉の匂い」のが白眉。これだよ、これ。 これは久世光彦による「ツィゴイネルワイゼン」( 映画のね )だね。死者たちのつかのまの宴。 女衒で始末屋の主人公清蔵が、本当、悪い奴。素敵。女殺しだね。久世光彦は酷薄な男語り小説が一番面白いと私は思う。 (記・2008.6.8)
 ◆ 皆川博子 「蝶」 (08.12/文藝春秋)
◆ 皆川博子 「蝶」 (08.12/文藝春秋)いままさしく命の灯火の果てようとしている、今際のきわの老婆がそこにいるとする。 彼女は身を横たえ、眼を閉じながら、しきりと口を動かしている。苦しげなふいごのような息にまぎれた言葉未満の何かがそこからかすかにもれている。 混濁とした意識が、彼女に最期の夢を見せているのだろうか。陰鬱としながらも、あなたはそこに耳を寄せてみる。 かすかの音の無意味な響きに聞こえたそれは、じっと耳を済ませていると、やがて言葉の連なりに聞こえてくる。それは、幼時の深い傷痕。幼い頃に彼女の犯してしまった、おそろしく、かぐわしい、思い出してはならない、話してはならない、聞いてはならない、泥濘の底から湧き立つ泡のような、罪の告白だ。 まさか。あなたはおもわずはっとして顔をあげる。しかしその時、老婆は静かに息を引き取っている。それは真実なのか。はたまた悪い幻だったのか。確かめる術はない。 ――そのような一冊、といえばいいだろうか。原罪的エロスにみちたあやかしの傑作。うたと罪と幻によって彩られた八つの短編集。 死線を渡るときに誰しも見るだろう、夢幻と現実が混沌とまざりあった、美しく禍々しい、凄絶なる一瞬の景色。それを小説で味あわせてくれる。 それは久世光彦の短編集「桃」に近いタッチといえばいいだろうか。齢75を越えた彼女だからこそ作りあげることの出来た老人耽美の世界だ。みだりがわしく、血みどろであるのに、透明で乾いている。 物語の舞台はすべて戦前から終戦直後であり、描かれる世界は死や罪に蔽われている。それは、その時代を少女として生きた作者自身のリアルが投影されてもいるのだろう。 片目のない男の、虚ろな眼窩に挿しいれられるたくさんの紫陽花の花。イギリス将校を殺して奪った一丁の拳銃。バグパイプになった網元の少年。大陸がえりの麗人の裸身に走る幾条もの陵辱の痕と、震えながら触れる少年の手。蝶を食べる女。オニヤンマの首の勲章。戦災孤児は桟橋に座り波に踝をなめられながら挫折した詩人の幻を見、幼女は傘の先で憎い友達を刺し殺し、特攻崩れの青年は白黒ショーで日銭を稼ぎ、美しい女ふたりは布団の中で湿った抱擁をくりかえす。 生者は苦しみもだえ、罪を重ね、死線を越える。残された者は死者を忘れる。しかし、いつしか彼らも冥界の海にたどりつく。そしてうすぼんやりした靄の向こう、影も形もはっきりしない所へと、全ては遠のいてゆく。なにもかも跡形もなくなっていく。残るのは蝶の羽ばたきの鮮やかな残像だけだ。 (記・2010.6.13)
 ◆ 赤江瀑 「遠臣たちの翼」 (86.10/中央公論)
◆ 赤江瀑 「遠臣たちの翼」 (86.10/中央公論)耽美派芸道小説? 世阿弥に魅せられた表現者たちの辿った数奇なる美と破滅の光芒――っていうとなんか本の帯みたいですよね。 赤江さんの本、何十冊と読んでいて今更言うのもなんだけれども、この人の話、やっぱようわからない。 文の巧みさ、華麗さに魅せられて読んじゃうんだけれども、読後の印象がわりとおんなじというか、 赤江さん、本当に若い男の肉体が大好きなんですね、というか。とにかく「うほっ」的なところ以外に訴求する部分が、わからんよ。 私が芸術家でないからいけないの? それともわたしがオチを求めているから? (記・2008.6.8)
 ◆ 栗本薫 「JUNE全集」 (95.07/マガジンマガジン)
◆ 栗本薫 「JUNE全集」 (95.07/マガジンマガジン)「JUNE」「小説JUNE」で書き散らした小説をどどんとまとめた全集。 ジュスティーヌ・セリエやらアラン・ラトクリフやら神谷敬里やら滝沢美女夜やらおバカなペンネームで発表した単行本未収録の作品もどどんと収録。 古式ゆかしいヨーロピアン少年愛――というか風木風あり、和風時代・衆道モノあり、ゲイ雑誌告白小説風――というか三島風私小説あり、と色々あるけど、結局全部薫印な濃厚JUNE。ニ段組で函入り上製本、定価3500円。 久しぶりに本気汁の薫を堪能して気づいたことがあった。 1 本気になると、登場人物がキモくなる。 2 本気になると、登場人物がみんな栗本薫(――というか、山田純代)そのものになる。 つまり、キモオタの純代である攻の青年が、キモオタの純代である受の美少年を 「をををを、お前は、俺とおんなじ種族。俺たちにとって、この世は、あまりにも過酷な世界。そうだろう――」 とかいって、頬すりすりしている、という世界なわけで。 脚本・演出・主演・助演・脇役、カメオに至るまですべてが純代、100%純代印、純代オンステージ、純代発・純代行きの夢列車、という感じになって、まぁ、あまりにも素敵過ぎます。 編集からの頼まれ仕事とか、作者の思い入れのあまりない作品だと、キモ臭はかなり抑えられているんだけれどもね。やおいとか、本人が書きたいから書いている作品となると、とどまることを知らない。 「翼あるもの」とかもさ、巽さんが、藤竜也イメージのはずだったのが、唐突にお面がぽろっと取れて、地金の栗本"キモおた"薫があらわれて「ををををっっ」とキモい心情吐露をだらだらするのとか、非常に素敵としか、いいようのないわけで。 ――まぁ、このねっちりねっちりしてキモいところが私が薫から離れた要因なのかな、と改めて認識した。 面白いかと問われれば、面白いんだけれども、なんというか、やっぱ、疲れる。 めんどくせーー、って思ってまう。 そんないつまでもぬちゃぬちゃしている子には、晩ごはん作ったげないわよっ、とかいいたくなる。 とはいえ、薫の大ファンはその粘着質でうっとうしい部分こそがツボなようで、 近頃、休日になるたびにかおりんの大ファンの家人と「どうして栗本薫はダメになったのか なにが栗本薫をダメにしたのか」と数時間しみじみ語り合っているのだが、彼曰く、 「キモくない薫なんて、薫じゃないよ」 「薫の小説のキモさは、薫だからこそのオリジナルな個性を感じる」 とーー。 まあ、ただ問題なのは、キモい面白小説を書いていた人が、いつまにか、本人がキモイだけのつまらない小説を書く人になってしまったという、それだけなのかな、と。 ともあれ、がんばれ栗本薫。と女性週刊誌の記事バリに唐突な心のない声援で〆る。 (記・2006.08.25)
 ◆ 紫宮葵「とおの眠りのみなめさめ」 (00.04/講談社ホワイトハート文庫)
◆ 紫宮葵「とおの眠りのみなめさめ」 (00.04/講談社ホワイトハート文庫)春の眠りは浅く甘く心地いい。ここ数日、うっかりするとうたた寝ばかりしていて仕事にならない。てわけでこの本を読んでみる。第七回ホワイトハート大賞受賞作で、著者のデビュー作。テーマはタイトルにもあるように「眠り」だろうな。 田舎の、その昔は一帯を治めていたという因習深い素封家が舞台で、主人公は翳りのある蒲柳の質の美少年で、母は若く美しい気狂いで、父は若き画家だったのが母に殺され、だから母は時々主人公を父と勘違いし、祖母は主人公に対して厳格で酷薄で、主人公と血のつながりのない伯母は本家を乗っ取ろうと画策し、その娘の従兄妹は主人公の嫁になるべく育てられていて、とはいえ本当に主人公が好きなんだけれどもそんなゴタゴタもあって素直になれないツンデレ美少女で、でも本当に主人公が好きなのは代々この血族の典医をつとめる家の、同い年の幼馴染みの爽やかイケメンで、そもそも血族には不思議な古くからの言い伝えがあって――。 という、どう考えてもど真ん中のJUNE、榊原姿保美の「龍神沼綺譚」、栗本薫の「絃の聖域」バリの世界が展開されて、こりゃたまらんわいと読みすすめていたら、最後に意外な展開。ドロドロとねじれた人間関係の末に殺すの殺されるのの展開なのかと思ったら、見事にひっくり返された。 この最終章は、硝子のくだける瞬間をスローモーションにしたように、妖しく美しい。 手垢のついた、とはいえ確かな需要のある耽美小説としての役割も満たしつつも、この最終章できちんと幻想文学にもなった。お見事。加藤俊章の典雅で妖しい挿画に相応しい作品になっている。 ちょっと文章からは自分の技量以上の「耽美」をしている背伸びの感があって危なっかしいけれども――もう少しだけ平易な文体の方が、自分らしさが出せるんじゃないかなぁ。次の作品も読んでみよう。 (記・2009.03.27)
 ◆ 紫宮葵「黄金のしらべ 蜜の音」 (00.12/講談社ホワイトハート文庫)
◆ 紫宮葵「黄金のしらべ 蜜の音」 (00.12/講談社ホワイトハート文庫)前作に続いて、ホワイトハートで今回は東南アジア風JUNE。 地上天。大規模リゾートとして開発されたこの常夏の南島は、革命で追放された王族たちの最後の許された土地でもある。島に忍び寄る不穏な死の影。淀んだ沼から途切れ途切れに聞こえるカストラートの誘うような幻の歌声。過去に生きる種族たちのかそけき夢の切れ端――というこんな感じの、耽美ぃな感じのお話で、ストーリー自体の意味はなさげ。 主人公の瑞麗(ルイリィ)の、最後の皇帝の落胤でありながら盗みと鴉片と売色の愉しみを知る悪徳の美少年っぷりと、幼時の瑞麗を暗黒街から見つけ出して王族の貴公子として磨きあげた叔父、雷鏡(レイジン)のヘタレ受っぷりに萌え萌えするのが一番の楽しみ方かな。上品におさまった「夏至南風」(長野まゆみ)といったところか。 物語は、はじめは従僕たちの飼う蟋蟀が死に、次に皇太后の愛犬が、その次には鴉片漬けの老いた庭師が、さらに皇太后が、忠実なる老執事が、と次々と忍び寄る妖しい死の影、その原因に辿りついた時――え、なにそれ、というちょっと残念な展開が待っておりましてね。多分ね、これ、設定とか人物とかはきちんとこさえていたんたろうな。 前半の地上天の豪奢で爛れた感じ。夏前のすがしい匂いと妖しい予感。そこに住まう最後の王族とその従者達の、ぬかるんだ泥のような頽廃と滅びの気配。そういうのはきちっとリアルに迫ってくるんだけれども、肝心の物語の核心にいたるところで、あ、このあたり考えてなかったな、というテンプレなオカルト展開で萎えます。もったいないなぁ。 ここまで世界を作ったのだから、ハンパなハッピーエンドでお茶を濁さず、もっと踏みこんで欲しい。もっと泥をかぶって血まみれなってほしいぞ、と。お綺麗なだけで「耽美」になると思ったら大間違いなのだ。 (記・2009.03.31)
 ◆ 榊原史保美 「蛇神 ジュナ」 (95.11/青樹社)
◆ 榊原史保美 「蛇神 ジュナ」 (95.11/青樹社)YES、これもJUNEだっ。大学受験でバタバタしていた頃に出てて、買ったはいいもののすっかり読み損ねていたんだよなぁ。 橘亮平、東都新聞の若き記者。ある大物政治家の一大スキャンダルを追いかけていた彼は、圧力により京都・山科の通信局勤務という閑職に追いやられていた。大手新聞の政治部記者という花形から一転、長閑だが虚ろな日々を送る彼の元に先輩記者の島村が訪れる。もし時間があるなら、失踪した義弟の消息を調べてくれないか――。 という、ふりだしではじまりますけれども、いっつもの榊原テイスト。 京都の山奥深くにある、秘匿された人を食う蛇神「ジュナ」と、幻の信仰に支配される因習深い村人、その一帯を治める旧家同士の因縁が血腥い政治闘争へと広がり――、って、榊原作品で何度もこういう展開、見たっっ。んで最後は、夢幻的なシーンに派手な大道具の崩壊があって、主要キャラのひとりふたりが死んだりなんかして、色々とすべてが丸く収まって、主人公は真実の愛と魂の救済とかそういうのにたどり着いて、終わり。「龍神沼綺譚」はもちろん「鬼神の血脈」とか「魔性の封印」とか、彼女の長編の半分はこういうのだよな。隠れ里の旧家でなかったら、家元とか(笑)。 榊原作品の楽しみ方ってのは、ミニマルミュージック的なんだと思う、同じモチーフを使いながら、仔細な――しかしそれまでと同じではない絶対的な変化が必ず作品にあって、その変化に、作者の心の成長が、自己受容への道程が垣間見えるのだ。 今回の作品の一番のポイントは、榊原作品にはほぼ毎回登場する、主人公を悪魔的な想念や欲望へと誘惑する年上の男性(――「トーマの心臓」で云えばサイフリートね)のありようかな。 その、サイフリート的ポジション、雑賀さんって人なんだけれども、もうなんというか、素敵やん、としかいいようのなくってっっ。超絶イケメンのすっげぇ悪漢、まるでメフィストフェレスのように、人の弱みにつけこみ、容易く陥れ、堕落させることを、眉ひとつ動かすことなくできる冷徹な悪魔キャラなのに、ただひとつ、主人公の橘亮平を愛してしまったばっかりに、物語が進むにつれどんどんきもくなっていく様は、悲惨過ぎて笑えてしまう。もうね、この本は雑賀伝説ってタイトル変えても何も問題ないですよ。 祖父と父を「ジュナに食わ」れ、旧家の跡取りから一転、養父の性奴隷として過ごした少年時代の雑賀さん。ジュナ神を祀る関西実業界のドン・丹波家への復讐を完遂させ人生の勝利者となる、その為にどこまでも冷徹になり、全てを目的のための手段としてきた雑賀さん。いまや丹波家と敵対する関西の大物政治家の懐刀にまで成り上がった雑賀さん。なのに、いや、だから、なのかな、少年期に自分と似たような疵を作りながらもどこかのほほんとしてKYなおぼっちゃんの主人公・亮平に惚れて惚れて惚れぬいて人生を台無しにしてしまう。 雑賀さん、作中「あいつは魔性だ」とかなんとか彼を糾弾してるんですが、もうね、どこがやねんっていう。あなたの盲愛はわかりましたから。 でも、肝心の亮平は、貢って言うくそつまんねー病弱の美少年(――しかも雑賀さんのお手つき)に一目惚れして、君は僕の運命の人だとかなんとか上ずったりしてて、もぅ、雑賀さんの気持ちわかってやれよなっつーの。つか、お前の、どこまでもどこまでも雑賀さんを受け入れない姿勢がイラッと来るっつーの。 そんなすれ違いの果て、雑賀さん最後に大爆発。拉致ってレイプして俺と一緒に死んでくれェェ展開へ。しかし雑賀さん、いざというところで都合よく利用する為だけに寝た男にあっさり刺されてしまう。 「誰が他人なんかに渡すか。おまえはここで死んで、今度こそ俺だけのものになって生まれ変わってくるんだ」 背中にナイフが突き刺さった瀕死の状態で、それでも亮平に襲いかかりながらの、これが雑賀さん最後の雄叫び。 来世でもストーキングするか……。届かない愛って、激しくて、きもくて、だけども泣けるよね。 元々、榊原作品において、サイフリート的キャラってのは、あんまりいい目を見ないのが通例なんだけれども、彼もまた不幸な人なんだなと、ここまで読み手を共感させたのはこの作品だけなんじゃないかな。その分主人公の感じ悪さってのはハンパないのですが。おっっまえ、もっと人の気持ちわかれよなっっ、勝手に貢とらぶらぶになってよがってんじゃねぇっ。少しは雑賀さんと召子ちゃん(――この人も亮平にほれてしまったばっかりにかわいそうなことになってしもうたよなぁ……)の気持ち、汲んでやれよっ。 ともあれ、前半の、関西を牛耳る大物政治家の懐刀という表の顔とうらはらに、その政治家と肉体関係をもちながらもその息子・娘たちをたぶらかし、激しい肉欲と甘い囁きで彼らを誘惑し、周囲の全てをコントロールするスタイリッシュ・アンド・デモーニッシュ雑賀。後半の、やっぱり昔の恋人・亮平が大好きで忘れなれなくって、でもどうしようもできなくって、もう、わけわかんなくなっちゃう、きもいぃぃ悲しきストーカー・雑賀。このギャップだけでごはん何杯でもいけるよねっていうJUNEでした。 話自体はいつもの榊原なので、お好きな人にはたまらないだろうけど、ダメな人はダメって感じ。宗教的、形而上的な魂の救済とか命の意味とかぐちゃぐちゃとした記述が多いのがちょっとうざったいかね。 そのあたりは「風花の舞」「荊の冠」のほうが、同じく記述は多かったけれども、テーマと物語が一致しててすっと入ってきた。 ただ、ジュナ祭の夜、神域に渡った「蛇子」が彼岸へと渡り、そして帰ってこなかったという一幕の、その風景は、幻想的で、なぜか泣きたくなるような清澄な美しさにみちている。 「龍神沼綺譚」の最後、池の面に手を差し入れて夢見るように微笑みながら静かに絶命していた若い男と、その池のほとりまでてんてんと続いた、彼を愛した少年の、血の足跡。あのシーンをふと思い出した。 榊原史保美は、あまり哲学的、宗教的で説明的にならずに、もっと直感的、映像的であってほしかったなぁ。「史保美」に改名して以降の末期の榊原は理屈っぽくって作品的にも袋小路であんまり好きになれないけれども、それでも不意に描かれるこうしたシーンは、やっぱりいいのだ。映像的でありながらどこか奥底の知れない妖しさと哀しみがあって、いまだに忘れられない。 あと、次作「ペルソナ」は今作のスペックダウンバージョンなんだな。「ペルソナ」で描かれた土俗宗教の教義であるとか、舞台、旧家の政治的な対立構造などなどあまりにも同じ過ぎて――それでいて粗製で、物語も全然整理されていない。雑賀さんもいないから(笑)こっち読んだら「ペルソナ」は読む意味ないかも。 (記・2009.06.18)
 ◆ 榊原史保美 「ペルソナ」 (97.03/双葉社)
◆ 榊原史保美 「ペルソナ」 (97.03/双葉社)「自分にとってJUNEってなんだったんのかなぁ?」 栗本御大の死を契機にふとふたたび思い、未読のままだったこの本を読んでみる。うん、これ、失敗作だね。 わたしは榊原さんの作品が大好きで、ほぼ全ての作品に目を通しているから、この作品で何を言おうとしているかなんとなく掴めるし、どうしてこういう人物なのか、こういう設定なのか、こういう展開なのか、というのが理屈でなく了解できるところがあるけれども、そうでない一見の読者には、説明不足で理解不能なところが多すぎるし、そんなファンのわたしからみてもご都合主義が鼻につくところが散見しているように見える。 唐突に主人公のために漢死にする本当は妾腹の兄だったボティガードの彼とか出されても、え、なにそれ? ですよ、この展開では。ほんっっとに読者への説明が全然足りていない。色々とつめこみすぎているし、色々と書き急ぎすぎているし、色々と踏み込みが足りない。 そもそも榊原史保美(姿保美)といえば耽美的で映像を喚起させる文章が特長の作家だと思うけれども、そんな彼女の小説が、なんでこんなにカギカッコばっかりで、しかもどれもこれもが説明的な長台詞なんだ? 第一章で不可解な殺人事件が起こる。まぁ、そこはいい。けれども、次の第二章で物語の重要人物が主人公の経営する画廊にとっかえひっかえ登場してはそれぞれの来歴を語り合っては退場するって言う、これはちょっと驚いたよ。 おかしい。こんなに小説がへたっぴな人ではなかったはず。 だいたい物語の核心である、秘境・雲居の里とそこにある幻の信仰と伝承、因習と濃い血脈に引きずられる者たちの悲劇――っていう、これ、ほんと、著者の初の長編作「龍神沼綺譚」以来のモチーフなんだけれども、「龍神沼」と比べて、全然のその世界が描けていないんだもの。なんでデビュー時点でできたことが、15年経ってできなくなっているんだぁっ。 なんだかんだいって榊原史保美的世界観が好きなわたしは、久しぶりのこともあってそれなりに楽しく読めたけれども、これは薦められませんぞ。 榊原さんはこの本のあと「やおい幻論」っていうこまったちゃんな自分語り本を出して、BREAKOUTシリーズっていう、「バンドやろうぜ」なバンギャの健全妄想ラノベ書いて、女性を主人公にトランスセクシャルをテーマにした長編JUNE(――といっていいよね、これも)「イヴの鎖」を発表して絶筆。 彼女は自己受容の手段として小説を書いていた部分のとりわけ強い人だと思うけれども、もう多分この頃はすでに小説を書くということにそういった役割を見出していなかったのかもしれないなぁ。妄執とか情念とか、そういうものに裏打ちされた緻密さが作品にないのだ。 ま、なにかと破滅の美学に飲み込まれる榊原世界において、主人公の千明ちゃんと大介がしあわせになって終わったのが、このお話の一番の救いかも。でもこれ、まごうことなく男女カプだよな。実際肉体も精神も女性だしな、千明ちゃんは。 でもそれでいいのか、JUNE。 (記・2009.06.03)
 ◆ 嶽本野ばら 「デウスの棄て児」 (03.06/小学館)
◆ 嶽本野ばら 「デウスの棄て児」 (03.06/小学館)超解釈による天草四郎一代記。 すっっぱらすぃっっ。豪速球ど真ん中のこれこそJUNE。栗本薫・榊原史保美・江森備・萩尾望都・山岸凉子、このあたりのラインナップがお好きな方にはたまらないだろう一冊。JUNEは自己の存在を賭けた闘争なんだよな、ということを再認識させられた。 前半、望まれぬ子であった天草四郎に次々と襲い掛かる苛烈な運命、そのたびに魔性の階を一段ずつ上がっていく様が凄まじい。 悪魔の子と罵られ、この世のどこにも存在を認められない彼は、この世の理の全ての闇を知り、そして魔少年となる。生血がどくどくと溢れるような激しい憤怒と憎悪。キリスト教徒をひとり残らず血祭りにあげる、そのためだけに、彼は島原の乱を引き起こすのだ。 味方であるはずの島原の乱の首謀者たちを四郎が謀殺するさまの激しい筆致は、これ「日出る処の天子」「江森三国志」等と同等にして圧巻。すっげぇ。 彼の、神を、宿命を、否定すること、この世の生きとし生ける者を否定し、哄笑し、侮蔑すること、それが自らの存在証明となるという哀しみ。「ここにいてもいい」「ひとりきりではない」「生まれてよかった」ただそれだけがほしくて、だけれどもそれだけがどうしても手にはいらなくて、ひたすらに心が冷え、その分理に冴え、鋭く人の心を刻んでいく、四郎は悲しい生き物だ。これこれこれこれ。これがJUNEですよ。 しかし彼は神を詐称することで、本当に信徒たちの神となってしまう。彼が苛烈な宿命の最中、常に抱きしめる腕を望んでいたのと同じように、信徒である彼らもまた、抱きしめる腕を、探していたのだ。そのようにして彼らは、ただ静かに穏やかに心を抱きしめ、お互いを救いあうようになる。 原城落城前夜、死を決した信徒たちに向かって「棄教し、城を出ろ」と叫び、十字架を折り、キリストの絵を踏みにじる四郎と、それにただ涙するしかない信徒たちの姿は壮絶だ。 ラストシーン、紅蓮の炎に包まれた原城で四郎は叫ぶ。それは勝利の凱歌だ。 「天主よ、私は貴方に勝ったぞ」 人の心の温かなぬくもりを、信じあう確かな心を、神でも魔でもない、愚かでささやかな人という生き物であるからこそ、手に入れることができた。全てが安らかで暖かいこの場所を、永遠に孤独な神にはわからないだろう。だからこれは、まぎれもない勝利なのだ。 おらしょの響きの中、彼の、神への長い戦いは終わりを迎える。 宗教の――だけではない、愛の、人の生の、光と闇が、この一冊につまっている。 ただひとつ苦言を言えば、作者はこの物語をあまりにも書き急ぎすぎている。この二倍の文量があってもいい。 宗教の欺瞞、人の世の欺瞞、それらはリアルに伝わってくるのだけれども、ポルトガルの、天草の、原城の、それぞれの情景の描写が薄い。読んでいても脳内に景色や匂いや気配がぶわっと広がる感じがしないのだ。空気感というか、「今わたしは物語の中にいる」と読み手に思わせるライブ感があったほうが、この話は絶対いい。それは物語の歩速を若干緩めて、ちょっと描写を緻密にするだけでできることだ。 あと後半、四郎が山田右衛門作や周囲の巫女らとの関わりをもって、いつのまにかひとつの救済を得ているところが少々唐突に感じる。憎悪と憤怒の化け物だった四郎が、なにがあったというのもないのに突然、憑き物が落ちて、普通の少年になってしまっているのだ。わかる人にはわかるけれども、なにかひとつでもいいからエピソードを置いて、もうちょっと説明したほうがもっといい。 このあたりもっと書き込まれていたら大傑作JUNEになっていたはず。 あとJUNEッ子のまこ的には、自らユダとなった右衛門作と四郎との絶対的な関係性をもっといっぱい描写してほしかったぞ。と。でもまあ、これだけでも充分に楽しめる濃厚良質JUNE。JUNEッ子は是非もなく読むべし。今の時代、むしろJUNEは乙男が書くものなのかね? 最後に解説の橋口いくよ。お前、ちょっと空気読め。なに作者に媚売った甘ったれた「あらすじ解説」してんだよ。しかも無駄にぶりぶりだし。そういう作品じゃねぇだろ?気づけよ。 (記・2009.06.08)
 ◆ 嶽本野ばら 「エミリー」 (02.04/集英社)
◆ 嶽本野ばら 「エミリー」 (02.04/集英社)「レディメイド」「コルセット」「エミリー」の三篇収録。 ・「レディメイド」……素敵な殿方と美学談義しているうちにいつしか恋に発展してミャハッ☆……っていう、野ばらちゃんのためだけにある妄想掌編。徒然草以来の典型的なオカマ日記。 ・「コルセット」……死ぬ死ぬ詐欺の青年が地雷女と恋に落ちて死ねなくなってしまいましたよという話。 ・「エミリー」……いじめられっ子のゴスロリ少女といじめられっ子のゲイ少年がいろいろあって恋に落ちたけれども、性欲の不一致でセックスはできませんでしたよ、という話。 ええいっっ。うっっっといしぃわぁっっっ。 わたしが先日あげた「デウスの棄て児」の感想を読んだ友人から、「『デウス〜』はJUNEだったかもしれないけれども、野ばらちゃんは本質的にJUNEっ子ではないよ」との密告を受けたので、続けて読んだのがこれ。たっっしかにこれはJUNEではなかった。てか、うざかった。ブランドの固有名詞だとかファッション・モード・美学談義だとか、そういうトリビアルな部分が、特に。 なんだろー。この人結構年行っているのかな? ファッションやらなんやらの劣化の早い文物の列挙とか、それこそ田中康夫の「なんとなくクリスタル」とか、中森明夫の「東京トンガリキッズ」とか、ああいう80年代のイタイ系の雰囲気なんだよな。YMOとかニューウェーブとかニューアカとかへんたいよいこ新聞とか宝島とか若者たちの神々とか、そういう時代の雰囲気をそのまんま。現代日本の少年少女を扱った作品だけあって、ふっとした描写に「古さ」があるんだよね。この感覚は、この経験は、明らかにわたしよりひとまわり以上は上の世代だな、って肌で感じる。そこはかとなく漂う橋本治な自意識の塊的めんどうくささも、実に80年代的でね。80年代を生きたゲイのサブカル好きッ子の心象風景、みたいな、そんな一冊。これが確信犯ならいいけれども、別に野ばらちゃん自身、80年代オマージュのつもりはないんだろうあたりがちょっとイタい。 三島由紀夫賞候補になった「エミリー」も、うーん、どうなんでしょ。主人公・エミリーが中学校で恒常的にいじめられているっていう描写が古く、かつ漫画的なテンプレのデフォルメで「ねーよ」としか思えなかったわけで。そんな主人公・エミリーといろいろあった末、色んなところが盛り上がって、ラブホ行ってペッテングまで行ったけれども勃たずに挿入はできなかったっていうゲイの少年も、なんだこりゃ、っていう、ちょっと理解不能。このラストはいろいろと誤魔化している感じする。てか、やれないなら、ラブホ行くなよなぁっっ。 ただひとつ、冒頭のエミリーの心情吐露がいい。中学生くらいの、自分を表現する術をもたない少女の、お気に入りの服(すべて Emily temple cute 尽くし)を着て、お気に入りのブランドのショップのあるラフォーレ原宿の入り口の前でうずくまっている、ただ、それだけで、自分は自分となりそれだけで満たされるのだという告白。この、毎日ラフォーレ原宿の前に行くという、傍目にはおよそ無内容な反復でしかない行為が、しかし、彼女にとっての救済なのだ。このいじましさ、痛ましさ。これだけはストレートに真実で、この部分だけはさすがに心に刺さった。多分彼が少女に支持されているだろう部分ってのはここなんだろうな。 あとは、まぁ、なんか、色々と頭でっかちで面倒な野ばらちゃんをぎゅと抱きしめてくれる「でもそんなお前、可愛いぜ」って云ってくれる素敵な旦那様が早く見つかればいいよね、という、そんな感じ。 あ、そうそ。「コルセット」のひ弱でぼくちゃんでダメダメな青年の猛烈な死ぬ死ぬ詐欺っぷりは、はじけきれなかった頃の尾鮭=サーモン=あさみのよう(初期の「田園のSO・UTU」とか)で、そんなにきらいじゃないです。近くには寄らないけど。 (記・2009.06.14)
 ◆ 梨木香歩 「西の魔女が死んだ」 (94.04/楡出版)
◆ 梨木香歩 「西の魔女が死んだ」 (94.04/楡出版)昨年映画化して話題にもなった作品。いじめで不登校になった中学生の女の子が田舎のおばぁちゃん家のスローライフで自分を取り戻しましたよって話。いい話で丁寧に作ってあるのは確かなんだけれども、あんまり共感できなかった。 ここにあるのは、実際の人の世界ではない。「かくあるべき」という理想で掃き清められた、ファンタジーの世界だ。こんな田舎も、こんなおばぁちゃんも、こんな中学生も、この世にはない。少なくともわたしの認識する世界には、いない。 いじめで不登校になる子は、こんなにまっすぐに大人の言いつけを守ったり、あるいは大人とぶつかったりはしない。もっと面倒で小難しくって嘘つきで卑怯で始末に終えないものだ。田舎のおばぁちゃんだって、こんなにおしゃれで、物分りがよくもない。もっと老獪で、頑迷で、ダサくって、どうにもならないものだ。 そんないい部分だけでない悪い部分も含めた生きた人の気配がないから、ああ、これは嘘の世界なんだと思うしかない。んで、何事も自分で判断しろとか規則正しい生活をしろとか一日の計画を立てろとか、ごもっともな説教されても、ああ、もう、どうでもいわ、と鼻白んでしまう。フィクションの形をとった正論好きのナチュラリストの説教としかうけとれなかった。 田んぼと畑と山しかない片田舎を、失われつつあるこの世のユートピアとするような価値観って、あまっちょろいと、わたしは感じる。 田舎って、素敵な部分があるのはもちろんだけれども、それ以上に不便で、面倒くさいもの。自然が街よりも近くに感じるのは確かだけれども、その分、その威力がこちらに向いた時の恐ろしさはハンパないし、人間同士の距離が街よりも近いのもまた確かだけれども、その分、関係の糸は濃密に複雑に絡まりあい、トラブルになった時の陰惨さというのは目も当てられない。 そういった負の部分をまったくなかったことにするのは、実際に「田舎」を持たない根っからの都会暮らしの人のご都合主義に思える。 大島弓子に「青い固い渋い」という短編がある。田舎のスローライフに憧れた都会暮らしの一組の男女が、理想を追い求めて実際に田舎暮らしをはじめたはいいものの、自然の圧倒的な力と田舎の濃密で排他的な人間関係にボロボロになり、ふたりの関係すらも破綻しかけるものの、またやり直しはじめる、という話。わたしはこちらの方が、スローライフを真摯に求める者を描いた手ごたえのある話だなと感じた。 こういうメレンゲのようになめらかで口当たりがいい「エコロジー」幻想を子供向けの情操教育として、あるいは若い女性向けの癒しとして消費する傾向って、わたしは嫌いだ。女子供向けなんだから、綺麗なところだけを表現すればいいというのは、大きな間違いだとわたしは思う。 もちろんこれはわたしの勝手な価値観なので、ここに描かれた癒しの森にうっとりと眼を細める人をとがめたりなんてことはしませんがね。それはなにも罪のない行為なのだから。 (記・2009.06.07)
 ◆ 穂村弘「手紙魔まみ、夏の引越し(ウサギ連れ)」 (01.06/小学館)
◆ 穂村弘「手紙魔まみ、夏の引越し(ウサギ連れ)」 (01.06/小学館)これ凄い。「萌え短歌」だわ。歌人・穂村弘のもとに妹・ゆゆと黒ウサギ・にんにを連れてあらわれた謎の少女・まみ。彼女は毎日、午前と午後に一通ずつ手紙をおくってくる。それは不可思議な短歌の態をなしていた――という設定の短歌集。中身はこんなの。 「ウは宇宙船のウ」から静かに顔をあげて、まみ、はらぺこあおむしよ 高熱に魘されているゆゆのヨーグルトに手をつけました、ゆるして。 美しい指輪は足の親指にぴったりでした、報告おわり。 ママレモンで兎の檻を洗ってる、ふわあふ、ふわあふ、あくびになるわ 「十二階かんむり売り場でございます」月明かりの屋上に出る なめとって応急処置しておこう、うなづきあって舌を準備す なんだよぜんぜん食えるとこねえじゃねぇかと蟹に怒る ほむほむの心の中のものたちによろしく。チャオチャオ。まみ(紅しゃけ) 数百首の歌から立ち上がってくる架空の少女《手紙魔まみ》。その姿を、読者のそれぞれがふわわわとイメージして、やーん、かわうい、萌えるぅぅ、となる、そんな仕組みの短歌集といっていいかと。キャラクター小説ならぬキャラクター短歌だね。イメージとしては「綿の国星」のチビ猫の系譜のロリータ不思議っ子に間違いないね。 装丁のおしゃれ感からいって、サブカル狙いっぽいけれども、ロリロリなアニメ絵を挿絵にしてオタク狙いにしたほうがもっと受けると思う。ラノベの美少女では満足できなくなったオタクのための上級者向け作品。穂村弘の鋭利な言葉と読者のイマジネーションのコラボによる、淡いピンクの萌え短歌。他の作品も読んでみよっと。 (記・2010.03.19)
 ◆ 松尾スズキ「クワイエットルームへようこそ」 (05.12/文藝春秋)
◆ 松尾スズキ「クワイエットルームへようこそ」 (05.12/文藝春秋)芥川賞候補となった松尾スズキの最新小説。中篇。 なるほどね、こういう作品が、芥川賞候補になるのね。納得。 ひとことでいえば、松尾スズキの小説の中では、一番薄い。 彼の魅力の核たる「過剰性」というのは、きわめて低い。 どうでもいいディテールに凝る――そこに現代的なリアリティーがたちあがってくる、のが松尾スズキの良さだと思うんだけれども、 「良識ある大人の世界」では、それは、いらない部分なんだろうな。 わたしは、爪の先までびっしりうっとうしい人間なんで、松尾スズキの、むしろさわやかさすら感じる粘着質な筆致がとても好きなんだけれど、 松尾スズキのファンでない人には、これくらいの薄さがちょうどいいんだろうなぁ。 ってわけで、ストーリーもいつもの松尾スズキと比べると、極めて平明かつシンプル。 精神安定剤をオーバードーズし、精神病院の閉鎖病棟に強制入院されたひとりの女性の絶望(――それも、きわめて性的かつ反社会的な<文壇の求める、現代的な絶望>)と、そこからの社会復帰と、その舞台となった精神病院の閉鎖病棟、の物語になっている。 閉鎖病棟という設定は、極めて舞台にしやすいものなのだが――というか、舞台を見るように私は読んだ。やっぱりこの人、舞台の人なんだなぁ、 彼の真骨頂であり、大傑作「宗教が往く」と比べると、どうしても落ちるというか、文学おっさん好きする、 <文壇カスタマイズな佳作>という範囲を出ないものといわざるをえない。が、 ラストシーンは、さりげないながらも残酷なやさしさと力強さがあり、読後、心地よいカタルシスを感じる。 じっくり読んでも二時間強というお手軽さもあいまって、読んで差し支えない一品か、と。 個人的に、精神病院の閉鎖病棟の描写は、吾妻ひでおの「失踪日記」の3章、「アル中病棟」を思い出した――というか、こういうところってのは、どこもこういうものなんだろうなぁ、きっと。 あと、もいっこ、主人公の明日香、どう読んでも女装している松尾スズキにしか見えなかった、ってのはどうよ? (記・2006.06.12)
 ◆ 佐々木丸美「沙霧秘話」 (83.02/講談社)
◆ 佐々木丸美「沙霧秘話」 (83.02/講談社)「雪の断章」(斉藤由貴の初主演映画作品)の作者である佐々木さん。その昔、何度トライしても文章が入ってこず断念したのだが、はじめて読みきった。 この人の文章、乙女チックが過ぎるんだよね。いわゆる、大島弓子とかの24年組作家の作品に唐突に入るポエムってあるじゃん。アレが延々地の文で続いているという感じで、おのれの手持ちの乙女チックを5割増ぐらいでやってようやく世界に入れた。 で、読んだ結果としては、あまりにも納得できないので驚いた。 ストーリーもちょっとどうなのかなと思うのだけれども、この小説、いわゆる「一人称小説」―――「私」の視点で語られた物語、なんだけどその視点が途中で違う人にがらっと代わるのね。本当に唐突に。 最初はそれぞれの視点となっているキャラが変わるとき、一緒に場面も変わるからいいのだけれども、ある所まで行くとそれが頻繁になって「アレっこれは誰の視点なの」となってしまう。 これでも結構反則なのに、視点が変わっても、ずっとポエミー、ぜんっぜん世界観が変わらんのよ。 「一人称小説」ってのはある意味「ある登場人物の視点に立った物語」なわけだから、そこで語られる個人的で抽象的観念的な極めて閉じられたレトリックってのは、まぁ、その語る人がそういうキャラなんだという解釈で受け入れられるけれど、その肝心の語り手が変わっているのにずっと同じようにポエミーなんだもん。なんかね、凄く変、それって。 この作者、自分以外のキャラクターが作れない人なのかなあ、と、私は思った。 女性キャラはいわゆるポエミーなキャラばっかだし―――これは自己投影なんだろうなぁ、男性キャラはどれも影絵のように印象が薄い。 このキャラはどういう服を着て、どういう顔つきで、どういう趣味があって、どういうものの考え方をして、どういう癖があって、そういったものがまったく見えない。 みんながみんな似たようなゆるやかな弱電波の中で、ゆったり穏やかに暮らしているという感じ。それゆえにこの電波を受信してしまった者は熱狂的なファンになるんだろうけれども、私は無理だった。 小説の中に自分しかいないというのは、わたしには、ちょっとつらい。閉塞感を感じてしまう。 もちろんそこに、孤独だけれども満たされた、甘い羊水の中でたゆとうような甘美さを、認めざるを得ないけれども、わたしは、もっと確かなものを手掴みしたいのだ。 彼女は後に筆を折ってしまったという。そうなるだろうことは、この一冊だけでよくわかった。 時を止める秘法が欲しいという少女たちのための作家なのだろうな。彼女は。 (記・2003.09.24)
 ◆ 梅棹忠夫『文明の生態史観』 (74.09/中央公論社)
◆ 梅棹忠夫『文明の生態史観』 (74.09/中央公論社)大学時代に文化人類学の基本だからとひとまず読んだほうがいいと薦められたものの、タイトルがタイトルなだけになんとなくそのままにしていた。で、実際読んでみると、いやあ、確かに面白い。 ほぼ五十年ほど前に造られた世界史モデルなのだが、それは今もって新鮮。巨視的なスケールでばっさばっさと世界と歴史を切り裂いていく。 いわゆる西欧中心の単系的発展史観(――いわゆる唯物史観)が中心であった時代にこの論文が与えたインパクトは相当であったろうことは充分過ぎるほどわかる。 私は読みながら「では今の中東と西洋の関係とは??東南アジアの位置付けとは??」などと現代の世界の位相とを引き比べて色々と考えてしまったし。古典的名著ってのはやっぱりパワーが違う。 ちなみに今となってはメジャーな説である西洋と日本の文明の平行進化説ってのもここが出所。 ポイントの「文明の生態史観・序説」は正味30分ほど、精読しても1時間とはかかりません。文章も平易ですので、中高生でも理解できるでしょうし、(――――多分、中高生の頃の私がこれ読んでいたら感動していたね)機会があったらこの部分だけでもいいですから、是非手に取って読んでみてくださいな。梅棹史観をさらに押し広げたものに川勝平太著の『文明の海洋史観』というものがあるらしくこちらも面白そう。今度読んでみよう。 (記・2004.06.01)
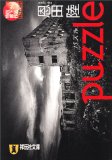 ◆ 恩田陸 「puzzle」 (00.10/祥文社文庫)
◆ 恩田陸 「puzzle」 (00.10/祥文社文庫)大好きな丸田祥三の廃虚写真が表紙なので買ってみた。中篇ミステリー。 長崎にあるかつて鉱山、今は廃虚の無人島・鼎島で見つかった謎の三死体。ひとつは電気の届かない廃映画館の客席で見つかった感電死体。もうひとつは、島で一番高い廃高層アパートの屋上で見つかった墜落死体。最後のひとつは廃体育館で見つかった餓死体。この不可解な三つの死体、死亡推定時刻はほぼ同じだという。はたして事故か事件か、真相はいかに、というもの。 90年代前半に新本格のブームってのがあって、その後にそれをテレビドラマ的に再解釈した「ケイゾク」とか「トリック」とかのテレビドラマが受けて、んでこれはその奇想天外ドラマミステリーをイメージした感じの作品っぽく感じた。 小説は「piece」「play」「picture」と大きく三部に構成されていて、「piece」が現場に残されていた謎の紙片――いわゆるヒント集。「play」が本文、検事二人が現場を観察しながら色々と考察している。んで「picture」がいわゆる解答編。つまり事件をひとつのジグソーパズルに見立てて、こういう構成にしているのね。これを筆者はおそらく企画書段階で決めておいたんだろうけど、肝心の中身をあんまり考えてなかったんだろうな。話自体が、もう、なんというか、ひどい。 話が核心にいたるにつれてどんどんとリアリティーが欠如していき、ナニコレ?感が増していく。探偵役の検事も、ロジック関係なく唐突にピコーンと正解引き当てすぎ。クイズ番組で正解あらかじめ聞いちゃってるゲスト回答者並みの不自然さ。 ネタバレすっけど、だいたい屋上の謎の墜死体が「暴風雨で竜巻的な何かがそこで起こって、人が巻き上げられてたまたまそこに落ちたんだよ」とかさ、どうなのよ。 長崎県の軍艦島そのまんまモチーフな鼎島の描写もちょっと薄く、廃虚フェチなまこ的にはもうひとつだし、中年の男検事二人の丁々発止も、乙女成分過多で絶妙にいらっときた。少なくとも日本のおっさんはこんな喋り方、しない。「逆転裁判」の御剣さんじゃあるまいし。 やーん、イケメンおっさんふたりが廃虚をアンニュイにふらふらしながら、ちゅっちゅしてるぅ――っていうだけの話だと思うので、BL臭だけでごはん何杯でもいけるって方以外は読むべきではないかと。BLでも、わたし的にはツボが違ったのでアウト。 (記・2010.08.10)
 ◆ 筒井康隆 「馬の首風雲録」 (80.01/文藝春秋)
◆ 筒井康隆 「馬の首風雲録」 (80.01/文藝春秋)筒井は文芸界のホームラン王です。やだなぁ、困っちゃうほど面白いなぁ。「旅のラゴス」系の一大スペクタクルロマン。戦争文学としてもトップクラスではなかろうか。 ここで描かれている戦争というのは、今現在、第三世界で行なわれている戦争そのもの。筒井文学は現実を予見している部分がいつもあるけれども、これもそうといっていいんじゃないかな。 もう、色々と上手いところがあって、細かく褒めたおしたいんだけれども、今読み終わったばかりでまともに紹介することができない。ともあれこれは読むべき。もっと多くの人に知られるべき作品です。 特に10代の感受性の強い時期の子に読んで欲しいなぁ。日本現役最高峰の大文豪・筒井康隆にノーベル文学賞を!!! (記・2004.09.05)
 ◆ 筒井康隆「美藝公」 (81.02/文藝春秋)
◆ 筒井康隆「美藝公」 (81.02/文藝春秋)この人は子供みたいなところがあるよなぁ、と筒井センセの作品を読んで微笑ましく思うのことが実に多いけれど、ほんっっとこれは微笑ましい少年の妄想小説。 これは映画の世界というものに少しでも夢を感じている人は読んだほうがいいかも。映画に対する愛だけで成立しているような作品といって過言でない。「映画、大好き」それだけがいいたい、素敵な小説なのだ。 筒井センセほど映画というものに対する愛はない私だけれども、筒井センセの思っていることは痛いほどわかる。わたしだって、この夢のようなキラキラした景色に憧れてしまう。でなければこんなに歌手や歌について語っちゃいないし。 途中演劇論議なんかが入るところは、後の「唯野教授」につながる感じかな。 (記・2004.10.31)
 ◆ 杉本苑子 「今昔物語ふぁんたじあ」正・続 (78.01/講談社)
◆ 杉本苑子 「今昔物語ふぁんたじあ」正・続 (78.01/講談社)そういえば子供の頃、一番最初に読んだ古典が「今昔物語集」だったなあ、ということを、思い出した。 個人的な印象から言うと、いっちゃん有名な今昔物語集の本朝・世俗説話の部分ってかなり、レディースコミック的だと思うんですよ(ってまたまた研究者が聞いたら噴飯モノの発言をしてしまう)、だから女性作家による今昔の再構築って作業はこれはどんぴしゃかな、と思いまして手にとってみましたが、やっぱりそうでした。 芥川センセを中心に色々と近代小説での今昔翻案モノはありますが、これもトップクラスのひとつなんじゃないかなぁ。 杉本センセは吉川英治師匠譲りの硬質で冷徹な筆致を持ちながら、いかにも女性作家らしい情念のどろどろっとした部分も持ち合わせているわけで、それがまさしく今昔物語のテイストにぴったりフィットしたっつうか、そんな感じでしたよ。 残酷だったり切なかったり、ほのぼのだったり、軽く笑わせてくれたり。人に対する描写力が確かなので、すうっと心に入っていって、楽しめました。大人のエンターテイメント小説。 (記・2004.11.02)
 ◆ 酒井政利・北島由記子「パラサイト」 (00.01/エムウェーブ)
◆ 酒井政利・北島由記子「パラサイト」 (00.01/エムウェーブ)郷ひろみのレビューを書いていたせいか、ふと酒井政利さんのことを思い出して、ひと昔まえワイドショーで話題になったこの本を読んでみた。が、ものすごく残念な作り。これ、ほとんどタレント本じゃん。適当に当時のワイドショーをネタにぐだぐだとおしゃべり。なんだこりゃ。 いちおう「世の中お互い様」という当たり前のことを「パラサイト」という言葉に置き換えて、すべて「芸能界だってお互い様よ」ともっていく、という一定した視座があるっちゃあるけれども、これってただワイドショーを見ているおばちゃんのお説教とどれほどの違いがあるのか、まったくわかりませんよ。 それにどうも全てのテキストが酒井氏の語りおこしっぽくって、鬱。しかも文章起こしたライターの人(―――共著となっている北島由記子の担当と推測する。彼女の姿は文中どこにも出てこない)が無駄に改行が多くセンテンスが短い、という典型的な安物週刊誌文体で萎え。 文体の重みは全く感じられないし、取り上げるテーマもデビ夫人が羽賀研二がという「どーでもいいですよ(@だいたひかる)」なもので、しかもそれらに対して「批評」といえるほどの深い考察もさほど感じられない。酒井氏の著書を何作か読んだことがあるけれども、こりゃないんじゃないのか。一番ひどいよ。 ワイドショーの騒動が熱いうちに本を出したいという気持ちはわかるし、自分で書くのがめんどいっていうのもわかるけれど、もっとちゃんとした人をライターに起用したほうがいいと思われ。急ごしらえにもほどがある。これで定価1400円はちょっとありえない。 郷ひろみも山口百恵も裕木奈江も久保田早紀も大好きだし、CBSソニーでの彼の活動は尊敬以外の何者でもないけれども、さすがにこの本は誉められたものじゃない。 唯一、この本で褒められるのはゴーストライターであり、表には絶対出ないはずの北島由記子の名前が著者として併記されており、彼女にも印税がしっかり入るであろうところ、それのみだろうと思う。これが酒井さんのいうところの「健全なパラサイト」ということなのか。 酒井さんが本を出すなら硬派な音楽・芸能批評、あるいは自身のプロデュースした作品に関する思い出語り(―――ってこういう本は今までも何冊か上梓しているんだけれどね)、これのみに絞ったほうがいいと思う。例えば郷ひろみや山口百恵など、各シングルごとにどこをターゲットにどういった経緯で作成し、結果今の自分の耳にどう響くか、と、売れなかった作品にもしっかり光を当てた詳細な全作レビューの本だったら、私ちゃんと定価で買います。むしろ出してほしい。 (記・2005.02.01)
 ◆ 唐沢俊一 「トンデモ美少年の世界」 (97.10/光文社文庫)
◆ 唐沢俊一 「トンデモ美少年の世界」 (97.10/光文社文庫)「まこ、グッジョブ!!」 先日、栗本薫ファンの友人に唐突にいわれた。 「唐沢俊一は栗本薫を読むべきだ」のテキストがよかったというのである。 彼女、唐沢俊一に対して否定的なようだ。 「ねぇ、唐沢俊一が『昭和ニッポン怪人伝』って作品でジュリーについて語っているから、それも読んで、感想書いてよ」 彼女は私がジュリーファンということも知っている。 「なんでよ、また適当なことかいてるだけでしょ」 「だから読んでほしいの」 私も、盗作騒動での彼の行動で否定的な感情を持つようになったひとりだけれども、なんでそんなアンチめいた活動をしなくちゃならないんだ、まったく。 とはいえ数少ない友人からのオファーなので探してみる、が、その本、図書館にも古本屋にも見当たらない。新刊で買う――のは、無・理。お金MOTTAINAI。というわけで代わりに「トンデモ美少年の世界」(97年/光文社文庫)という「JUNE」で90年代中頃に連載していたコラムをまとめた一冊を手にする。これでいいだろう、友人よ。 もういい加減最近やおい本ばっか読んでてうんざりしてるんですけれども、と、倦怠気味に読み始めて瞠目、ちょっとこれ、ネタの宝庫ですやん。どういうことよ。 ひとまずJUNEで連載していたのにもかかわらず、JUNE・やおい・BL文化に関わることはほとんどテーマになっていないのが驚く。90年代中期という時点で、萩尾望都、竹宮恵子といった24年組作家も、森茉莉や栗本薫といったJUNE小説の先達も、榊原史保美や吉原理恵子といった初期JUNEを盛り上げた作家たちも、江森備や秋月こおといった小説道場出身作家も、高河ゆんや尾崎南、山藍紫姫子といった90年代初頭に同人ブームで名を挙げ商業転向した作家たちも、「星矢」「キャプ翼」「シュラト」「幽白」「スラダン」といったパロ同人において一大ムーブメントを築きあげたアニメ・漫画作品も、まったく彼は触れようとしない。はたしてこれらをまったく扱わないで、やおいについて語れるのか。ほとんど「残像に口紅を」だ、語れるわけないのである。 では、なにについて彼は語っているのか。 三島由紀夫のヌード写真が掲載された「血と薔薇」を、戦後直後に出版された同性愛の告白本「メモワール」を、60年代のゲイボーイの実態を取り上げた雑誌「ゲイ」を、13歳の少年の射精の瞬間を収めた写真集「少年期ハードスペシャル」を、10歳前後の少年がレイプされている洋モノの裏ビデオを、70年代後半のミニコミブームにあった男性向け少年愛誌「少年」を、語るのである。マジモノのゲイの、とくにペドフィリアの世界を、ねちっこく、唐沢本人の性欲の生臭さを漂わせながら、語るのである。「未成年の男の子を犯してみてぇぇぇ」文章から声なき彼の叫びが聞こえてくるようだ。唐沢俊一の、13歳の少年のエロ写真を執拗に追いつづけて、最終的には彼の射精の瞬間の修正前の生写真を手に入れるくだりを読んだ時に、わたしは思わず大声で叫んでしまった。「きんめぇぇぇーーーーーっっ」 この本を読む限り、彼は、真性の少年愛者としか思えない(まぁ、成人女性も好きなようなのでバイセクシャルなのかもしれないけれども、これで私はホモではないというてるのだから、頭が痛い、なんだその今お前が手にしている生写真はっ。え、ゲイでなくペドだから違う? むしろそっちの方が問題だろうが。ゲイは別に犯罪じゃないからお好きなようにでいいけど、ペドはダメ、ぜったい、だよ)。 何故、栗本薫をさして知らずに彼が嫌ったのか、その疑問はここであっけなく氷解した。「ゲイは腐女子が嫌い」。ただそれだけのことだったのだ。(――と、ここを件の友人からツッコミがはいった。違うよ。そこは「キモオタは腐女子が嫌い」だよ。って、えぇい。どっちでもいいわいっ!) まぁ、それはいい。彼が少年愛者でもなんでも、犯罪を犯さなければそれでいい。が、そのスタンスで知ったように「JUNEっ子はこういうが好きでしょ」と、あるいは「JUNEはかくあるべし」と、ぴんぼけな看破やら啓蒙やら読者にむけるのにはさすがに苦笑いを禁じえない。全然ちがいますよ、唐沢さん。普通のやおらーはあなたのように少年のアナルやペニスをねらってませんから。しゃぶったりしゃぶられたり、入れたり出したりしたがってませんから。そういう彼のとんちんかんぶりを笑うには、楽しいネタ本なのかも知れない。 おかしい点、トンデモな点をいちいちあげつらうには盛りだくさん過ぎるので、ひとつだけ一番間抜けなのを紹介する。 「悶え苦しむ美少年地獄の映画館」の回の唐沢の語る映画「ベニスに死す」ラストシーンの、「お前今すぐトーマス・マンとビスコンティーに土下座しろ」とでもいいたくなる、どうすればそんな解釈ができるんだというお馬鹿でトンデモっぷりも素敵だが、やっぱれこれ、わざわざ2回にも分けた大力作「セピア色の解剖」の回。 1953年に出版された同性愛の告白文集「MEMOIRE」に収められた星野英夫なる者の手による「少年時代」と題された、自らが旧制中学時代に体験したとされる性的いじめ「解剖」の話を大幅に引用して、唐沢が語っているのだが、その体験談というのが、どう考えてもペドのセンズリ用妄想を文章化したとしか思えない。 ねちっこく精液臭い描写を逐一無駄に引用してうんざりするので(――単なる紙数稼ぎか、あるいはこの文章にびんびんに興奮して我を忘れたのか。おそらくどっちもだろうな)、概要だけ書く。 プールの裏手で悪いクラスメート数人に捕まって裸に剥かれたよ→それだけであきたらず、しごかれて、フェラチオもされて、強制射精されたよ→アナルセックスされそうになったら、見かねた親友が助け舟を出したよ「俺が身代わりになる。俺のアナルを使え」→親友は奥の野球小屋でひとりずつ順番にレイプされたよ、そんな親友のレイプされてる時の姿はなんだか可愛かったよ→赤裸々な姿を見せ合ったふたりはそして親友から恋人へと発展したよ→おしまい よしんば事実なら、凄惨な性犯罪。とはいえ99%の確率で妄想と即断できるこの与太に、唐沢はこうコメントしている。 「……しかし、単なる解剖でなく、その後アナルセックス(しかも輪姦!)までごく普通に行われていたなんて、昔の中学生は進んでいたんだねぇ」 進んでいたんだねぇ……じゃねぇだろっ、おい。あ・り・え・な・い。まるっきり信じてやがる、こいつ。どう読んでも「だったら俺のアナルを」が超展開すぎるだろ、くそみそすぎるだろ。ホモの妄想与太話でないほうがおかしいだろ。さらに、こうも云っている。 「文章の心得のある読者なら、このシーンのこの設定で耽美小説が一本書けるだろう」 耽・美・小・説・を・な・め・ん・な。そしてこんなふざけたまとめ方をしている。 「いい年齢になってからの大人の性のねじれが問題になるのは、少年時代のこのような通過儀礼を体験できない情況に原因がある」 えぇぇっっーー!? つまり、ちゃんとした大人になるために少年はレイプの被害者になるべしってこと? なにそのトンデモレイプ推奨理論。唐沢、あんたがペドフィリアのハンターとして活動するにはその方がいいかもしらんがだね、そんな世界は、未来永劫絶対訪れないぞ。 もうね、とほほがすぎる。なにか、もう、この方は、純粋に電波さんなのかな、と。 ところで、こんなことも云っている。 「やおい小説に男性ファンが多いのも、それ(――手記のような少年姦)を追体験したいからなのでは」 やおいに男性ファンか多いってのは、初耳だなあ。わたし、一般書店でも、「まんだらけ」のような漫画専門店でも、コミケなどの同人誌即売会でも、いわゆる女性向のやおい作品コーナーに男性客が大勢群がっているところ、全然見たことないんですけど。せいぜい最近少しは見かけるな、程度ですけれども。唐沢俊一の言う「やおい」って、わたしや世間の判断する「やおい」と違うんだろうな、きっと。そうとしか考えられない。唐沢さんの世界の「やおい」は、三次元の少年を犯したいけどできないペドフィリアの代用品なんだろうな。うん。 と、まあ、こんな感じで、他にもとほほで頭痛いテキストがいっぱいあるので、ヘンテコな人をウォッチしたい人でやおいに詳しいなら、読んでみるといいと思うよ。え、わたし? わたしはもう、うんざりです。おなかいっぱい。 それにしても、本当、どう考えても不思議なんだけれども、なんでこんなトンデモ物件が、「と学会」にいるんだろう。唐沢俊一はどう考えてもバードウォッチする人でなく、ウォッチされる鳥だろうよ。 (記・2009.06.21)
 ◆ 大塚英志+東浩紀 「リアルのゆくえ」 (08.08.19/講談社)
◆ 大塚英志+東浩紀 「リアルのゆくえ」 (08.08.19/講談社)対談のつもりが糾弾されたでござるの巻、という一冊。 ふたりのオタク評論家が、現代を、オタクを語るというテーマなのだろうけれども、プロレスマニアでもある大塚英志は多分、ここで対談という名の言葉のプロレスを仕掛けるつもりだったんだろうな――彼って、相手を挑発するような確信犯的な言い方ってよくするしね。それぞれのイズムとイズムのぶつかり合いによる一回性のレッスルファンタジー? みたいなそういうのをもとめていたんじゃないかなーと。ってまぁ、私もプロレスよく知らないんですが。 それに対する東浩紀は、大塚英志の仕掛けた技をきちんと受けてあげないし、もちろん自分からしかけもしない。基本「ですよねー」と話半分で大塚英志に相槌だけ打って、話のつながりの一切ない自分のことを話したりしてる、まるで主婦のおしゃべりのような東浩紀。これって対談として記録する意味あるのかと、前半部分はさすがの私も疑問を抱きかねなかった。 そんな、ずっとすれ違いで肩透かし、ロープに振ったのにこっちに戻ってきてくれない、みたいなじれったさの果てに、後半部では、ついに大塚英志がガチンコを仕掛ける。相手のために言わずにおいていた人格批判すれすれ、相手の退路を断つような発言をあえてしだす大塚英志、それに東浩紀は吃驚おろおろ、最後はほとんど涙目になって泣き言を言いだすのだけれども、しかしここの、煎じ詰めれば「僕だって頑張ってるんだ、そんなにいじめないでよ」といった類のおよそ評論家と思えないような言葉には、彼が頭でこねくりだした能書きのすべてを薙ぎ払うリアルが立ちこめている。彼の周りを取り囲む空疎な理屈――ポストモダンがどうちゃらというしゃらくさいアレはただの自己弁護にしか私は感じ取れなかった――がびりりと破れて、どろどろとした生身が溢れ出しているのだ。 彼の脆弱な理論、それは彼が自分を保つために必要なせいいっぱいでもあるのだな、と。彼の考えに共感はしないけれども、そうせざるを得ない逼迫した何かを理屈を越えた所で私はそこに感じた。 ただ読み終えて感じるに、きもくて冴えないオタクであることに腹をくくって衆目に晒している大塚英志とそんな自分にまだ言い訳してええかっこしている東浩紀ではそもそも同じ土俵で話はできないんじゃないかな、とも思った。東っち、あとがきで「なんでこんなに怒られたのかわからない(意訳)」的なこというてるし。 はからずも大塚の反則ぎりぎりの言葉の応酬によって漏れでた彼のどろどろと渦巻く生身――それを凝視し自らの言葉とし衆目に晒すことがきっと彼の飛躍の鍵なんだろうけれども――なんでこんな本が売れるのかさっぱりわからないとかサイトで言っているようだし、そこは難しい所か。 もっと自分を曝け出せばいいのになぁ、東浩紀は。そうすればもう一段階上の気持ち悪くって面白いオタクになれるのに。「傍観者でいたい」なんていつまでも子供みたいなこといってないでさ。 大塚英志の、今でもワンフェスで必死にフィギュア買い漁るような――しかもそれでいてまったく恥じないオタクっぷりをもっと学んでいただきたいぞ、と。 (記・2010.04.05)
 ◆ 「1946〜1999 売れたものアルバム」 (99.12/東京書籍)
◆ 「1946〜1999 売れたものアルバム」 (99.12/東京書籍)書籍・シングルレコード/CDの年間売上ベストテンを中心に、その年売れた商品戦後54年分を一気に総まとめ、というデータブック。や、これ、色々と面白いわ。 書籍のベストセラーの変遷とか見ると、終戦直後は、純文学とかあと哲学・経済学とかのいわゆる「お勉強」の本がガンガンランクインしている。「漱石全集」とか、今更のランクイン、かよ、と。その他、みんなが知っているこの手の作家、太宰とか三島とか谷崎とか、現役で書いててどかどか売れている。純文って、ヒットファクトリーだったんだね、昔は。 それが高度経済成長期にはいるとビジネス書とかが売れるようになって、オイルショック以降は占いとか予言とかのオカルト本が出てきて、80年代に入るとタレント本やらあやしげな自己啓発書やらテレビゲーム関連本やらヘアヌード写真集やらが出てきて、そして今、と。 ベストセラーで見ると、裕福になって、本の役割が「お勉強」から「娯楽」へ変化していったのが、戦後の日本ってことなのかな。 あと、結構、石原慎太郎って時代ごとに切り口を変えて世間に受ける本作りをしてピンポイントでヒットを掻っ攫っているんだなー、結構計算高いなーとか、ひばりちゃんは「哀愁波止場」のあと、60年代前半に西田佐知子やらスパーク三人娘やら弘田三枝子やらのアメリカンポップスのカバー歌手に追いやられる形で一度、軽く落ちてて、そのあと「柔」「悲しい酒」と思いっきり保守的な方向に針を振っていって復活したんだな―とか、色々と気づく所、多いです。 ちなみに、戦後最大のベストセラー作家は池田大作でした。……。1965年の「人間革命」から1999年の「新人間革命4」まで、実に30作近く年間ベストテン入りしてます。色んな意味で、凄い……。 (記・2010.04.02)
 ◆ 中江有里 「結婚写真」 (2010.11/小学館文庫)
◆ 中江有里 「結婚写真」 (2010.11/小学館文庫)元アイドル、現在女優兼脚本家の中江有里の処女小説。 結婚・出産のラストチャンスを迎えた40歳代前半、シングルマザーの母・和歌子、恋を知り染めた中学生の娘・満、ふたりは「友達のような親子」。ある日、母は娘に10歳年下のボーイフレンド・林を紹介するが……、というもの。 うまい。 母の、「女性」として終わりを迎えようとしている自らへの焦燥、娘の、芽吹きゆく「女性」をなかなか受容出来ない生硬さ。それぞれが女性として端境期にあって対照的であり、その佇まいが気まぐれに撮影した二葉の「結婚写真」に象徴され、収斂していく。 テーマとしては「親離れ・子離れ」なのだろう。章ごと交互に母へ娘へと物語の視点と転換させながら、母娘の複雑で微妙な共依存的関係を見事に描写している。 母が子に共犯的関係を強要する欺瞞――しかし、その先に一人で世間に立ち向かっている母の、一個の大人としての弱さや哀しさがほの見えるのがとてもいい。娘の家出を知り混乱する母の、葉裏が翻るように唐突に現れる、それでいて読み手に十二分に了承しうる弱々しさは白眉。 著者はそれを指弾するのではなく、それを認識し肯定し受け入れている。大人の話だな、と、私は感じた。 些細なきっかけでぐずぐずとなし崩し的に壊れる和歌子の淡い再婚の夢も、本当にありがちでリアル。 特に大きなエポックがあるわけでもない、地味で小さな、誰にでもあるような日常の物語だけれども、世の中って言うのはたいてい、陸でも海でもない、境目のはっきりとしない波打ち際のあたりであわあわと進んでいくわけで、その辺の微妙な人の世のグラデーションってものを、丁寧に描いている好作品だと思う。向田邦子の諸作が好きならば(――向田邦子脚本・久世光彦演出・桃井かおり/松田優作主演の「春が来た」を私は想起した)多分気に入るんじゃないかな。 (記・2011.06.05)
 ◆ 田原俊彦 「職業=田原俊彦」 (2009.05/KKベストセラーズ)
◆ 田原俊彦 「職業=田原俊彦」 (2009.05/KKベストセラーズ)30周年を記念して出版されたトシちゃんの自伝。いわゆるタレント本なんだけれども、結構率直に色々と語っているのが好印象。 ジャニーズ事務所社長・ジャニー喜多川氏のことをはじめ、独立の決意など、触れづらいこともしっかりと語っているし、タレントとしてのナルシシズムやら、自らのこれまでキャリアなどなど、結構、自らを客観視している(――88年の「教師びんびん物語」での再ブレイク前のプチ低迷時代なんかもちゃんと触れてるしね)。独立後、活動に見えない圧力を感じるようになったこと、しかしそれ以上に自らが解放された喜びが勝ったこと、なんかも書いてる。 早くに父を亡くし、極貧の母子家庭で兄弟とは離れ離れに。十五歳、人生の一発逆転を目指してのタレント志願。「田原俊彦・1000日計画」なるものを掲げ、高校卒業するまでにデビューすることを自らの目標とし、高校一年の夏に単身上京しアポ無しでジャニーズ事務所に直撃。運よく研究生になるものの、時代は「ジャニーズ・冬の時代」、本当にデビューできるのだろうかと不安を抱えながらの三年。それが一転「金八先生」で脚光を浴び――。というトシちゃんがデビューするまでの件は、結構熱い。 デビューして売れっ子になって、一番最初にしたのが父の墓を立てたこと、ってあたり、デビュー時点で完全に腹を括ってたんだな、トシちゃん。アホな子っぽいアハハ笑いのトシちゃんがある程度計算によるものだったことは薄々気づいてはいたけれども。 ジュリーのレコードひっそり買って友達に見られないように自宅で歌真似していた甲府の貧しい少年が、覚悟を決め、自らを磨き、いろんなものを捨て、運命の導きを掴んで、そしてスターになったのだな、と。結構泣けます。 ゆるい文体で所々おマヌケなエピソードなんかも織り交ぜちゃったりしてますがそれも含めてトシチャン。彼のことをよりよく知りたいならマストバイな一冊。 (記・2011.01.15)
 ◆ 佐藤明子 「沢田研二という生き方」 (2008.01/青弓社)
◆ 佐藤明子 「沢田研二という生き方」 (2008.01/青弓社)ジュリーマニアのおばちゃんのおしゃべり。それ以上でもそれ以下でもない。 話が全然整理できてないので、ループして同じ話を繰り返すし、牽強付会にジュリーと関係のない話に行って戻ってこないし、時系列関係なしに古い話と最近の話がぐちゃぐちゃになるし、説明不足のままあっちこっちに話をすすめるし、作者の心底どうでもいい自分語りはダダ漏れしてるし、なにをいわんとしているのか、まったく伝わってこない。でも、ジュリー好きではあるんだろうな、というのはわかる、という。だからおばちゃんのおしゃべり。 データらしいデータの提示もまったくなく(そもそも地の文自体、いつ・どこで・だれがといった5W1Hの基本ができてない)、およそ批評たるべき客観性というのはない。これでは「沢田研二の生き方」も感じ取れない。せめて年表を作って時代順に語るとか整理して語ればいいものを。 また鉄壁のジュリーマニアかというとそうでもないようで、「勝手にしやがれ」「ダーリング」などの全盛期にファンになって、85年の独立から89年の田中裕子との再婚前後に興味を無くし、ここ最近動画サイトやらファンサイトなどで再燃した――という感じっぽく、長年追い続けていたジュリーマニアだからこそ見える部分、分かる部分、というのもあまり感じられない。つか90年代のジュリーのスルーされっぷりが半端なくって、泣ける。この時代もいい曲いっぱい歌ってるし、いい仕事もいっぱいしてるのに(哀)。世間の話題にはならなかったけどさ。 そして何より一番不満なのが「歌手・沢田研二」なのに歌に関する部分が全篇に渡ってあまりにも薄いところ。ジュリーがどういう状況下で、どういう歌を歌って、それがどのように時代に影響を与え、後世に引き継がれ、といった部分は、ほとんどといってない。あの頃のジュリーはあんなだった、こんなこと言ったという、ビジュアルやら発言やら横のつながりやらおよそ枝葉末節ばかりが語られていて、まー、だから、スターとして輝いていた「沢田研二」という存在が好きであって、歌そのものはわりとどうでもいい感じ。そんなゆるめの顔オタのおばちゃんのおしゃべり、と思えば心安らかに思えるのだが、ちゃんとした読み物としてとらえるとイライラすることしきり。 人間・沢田研二を語るのはいいかもだけれども、彼は歌手で、歌にこそ天命があるんだから、そこをおろそかにしてどうするよ。もうっ。これで納得するほどジュリーマニアは馬鹿でもなければ、お人よしでもないですのことよっ。ぷんすかっ。 (記・2011.01.18)
 ◆ 銀色夏生 「テレビの中で光るもの」 (2009.08/幻冬舎文庫)
◆ 銀色夏生 「テレビの中で光るもの」 (2009.08/幻冬舎文庫)あの銀色夏生が、テレビ評。エリカ様やら「水曜どうでしょう」やら徹子やらを語る、銀色夏生。時代の移り変わりというものにちょっと呆然となってしまった。 いわゆる森茉莉・ナンシー関などなど連綿と続く「暇そうなおばさんが退屈なテレビを見ながらなんかしらぐだぐだ語る」というシロモノだが、銀色のそれは、お茉莉ほど自足している感もなければ、ナンシーほど世間様に毒づいてもない。 なんかこう、茫洋として不定形な感じ。時折はっとするようなひと言があったりするのだが、それは次の瞬間には霧散してしまう。雲の形が移り変わるのをぼうっと眺めるような、あわあわとしたテレビ評といっていいかと。 文才のある、テレビがとりわけ好きなわけでもないおばさんが、特にやることもないし、ひとまずつけてみて思ったことを、意味はないけれども書き残してみましたよ、みたいな。 どう思われようとかどう見せようとかどういう層に訴求しようとか、そういうものがまったく感じられず、とはいえ書き手の情熱も感じられない、という奇妙な一冊。なんだこれは。どこへ向かおうとしているんだ。 (記・2011.01.17)
 ◆ 川瀬泰雄「プレイバック 制作ディレクター回想記 音楽「山口百恵」 (2011.02/学研)
◆ 川瀬泰雄「プレイバック 制作ディレクター回想記 音楽「山口百恵」 (2011.02/学研)これは物凄くいい本。山口百恵の音楽が好きならばマスト、コレ読まない奴はバカ(おすぎ風)。山口百恵のほぼ全作のディレクションを担当した当時ホリプロ所属の川瀬泰雄氏による山口百恵全楽曲レビュー+当時の回想記。 たいていの業界関係者の回顧本って、当時の細かい部分とか、思い出補正かかりまくりでいい加減で、事実と違っていたり、あるいは時系列とか因果関係とかぐちゃぐちゃになってたり、あるいは主観はいりすぎてて、結局の所ただの自慢話したいだけ?ってモノが多いのだけれども(――誰のどの本が、とは言いませんがね)、この本は違う。ぜんっぜん違う。 百恵ファンサイトの管理者の手にしているデータを借り、また自らが記した当時の記録を押入れの中から引っ張り出し、関係者仲間(――編曲担当で川瀬の個人的友人である萩田光雄氏やらソニー側のディレクター・金塚氏など)から「あの時どうだったっけ?」と再度の聞き取りをした上での執筆であるようで、極めて客観的で正確。ファンが読んでて「川瀬さん、それ、事実関係違くない?」という部分は一切ないし、もちろん、「へー、こんなことがあったんだ」という裏話はどっさり。かつ一曲ごとにみっしりとレビューしている。関係者ではあるんだけれども、書き口がきちんと、批評家視点なんだよね。歌手・山口百恵をリスペクトし、きっちり真正面に受け止め、かつ一定の距離を保って、語っている。 ゆえに、出来がよくなかったものはよくないとはっきり断言。今振り返るにコレはこうすればとか、この時は迷いがあった、とか、こういう意図だったが仕上がりはつまらない作品になってしまったとか、真摯かつ率直に語っていて、クール。関係者の文章でコレができるってのは稀有なんじゃなかろうか。もっと情緒的で距離感取れなくなるものですよ、フツーは。 んでもって、個人的には、ここがよかった、コレはよくなかった、こう見立てる、この部分がツボ、といったところのいちいち「そうそうそう、やっぱりそう思ってましたかっ」と思うところばかりで(引退決定以前の「春告鳥」の頃の迷いとか、過密スケジュールゆえに荒れたボーカルが逆にドキュメンタリータッチに響く80年の諸作品とか、「花筆文字」「寒椿」「霧雨楼」「曼珠沙華」「夜へ……」「娘たち」「イントロダクション・春」とアルバムやカップリングのみで展開した純和風ロックとでもいっていい宇崎・阿木・百恵の作品でしか味わえない独自の世界観とか、「しなやかに歌って」より絶対「あなたへの子守唄(原題/しなやかに愛して)」だよね、とか)制作者である川瀬氏の視線と、山口百恵の音楽の1ファンである自分の視線とがきちんとシンクロしていたのがわかって、なんだか妙に嬉しかったりして。ここまでシンクロして楽しんで読めるってことは、翻っていえば、川瀬氏もまた一ファンとして心底楽しんで山口百恵の楽曲制作に携っていたのかなぁとわたしは感じた。 ともあれ、ひとりの書き手が、アイドルの楽曲をメインテーマに、しかもひとりのアーティストのみに焦点を当てて深く掘り下げた書籍っていう意味でも稀だし、関係者がひとりの担当アーティストに関してみっしりと語った書籍という意味でも稀。ちょっと他にないよ(――作ろうにも、ジュリーにしろ、聖子にしろ、明菜にしろ、レコード会社移籍・独立などで途中で担当ディレクター・プロデューサーも代わっているわけで、ゆえに関係者による全作レビューってのは無理筋なわけだしね)という一冊。読むべし。 (記・2011.05.02)
|