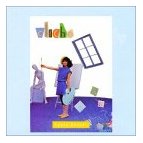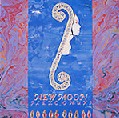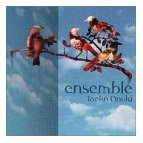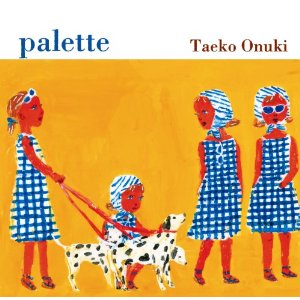大貫妙子の歌の子供は、ホンモノの万年少女、谷山浩子のような不気味さ、毒、反社会性はなく、またホンモノの万年幼女、矢野顕子のような、無意味性、過剰で悪意のない攻撃性もまたない。 彼女が描くのは、きわめて上品で体制に組しやすい優等生な子供像である。いうならば「大人がかくあるべきと思う理想的な子供」。彼女の子供向け作品にタイアップが多いのもけだし納得である。 お父さんお母さんも安心な良質な絵本。そんなアルバムになっている。7点。
ちょうどこのアルバムはこの先に訪れる小林武史とのポップ路線と『PURISSIMA』『Tchou !』のアコースティック路線が混交したアルバムといえるかもしれない。 「もう1度トゥイスト」などの大村憲司のGS調のギタープレイにはちょっと微笑んでしまう。(――これは同時期に大貫がプロデュースした安田成美の『Ginger』でも同じアプローチをしている)この延長線上に小林武史との共同作品『Shooting star in the blue sky』があるといっていいだろう。 一方ジャン・ミュジーの「木立の中の日々」や「HYMNS」は弦楽の音色が端正なアコースティックな世界。 その中にあって、国内では原田知世との競作となったエルザのカバー「彼と彼女のソネット」がもっとも光っている。7点。
溝口肇のチェロ、中西俊博のバイオリン、フェビアン・レザ・パネのピアノ、清水靖晃のサックスをバックに同時録音 (ちなみに サントリーホールでのライブ音源ではない、あくまで"ライブ音源風")。 無駄なものを殺ぎ落としたタイトなアコースティッククサウンドで、既発表の楽曲たちがよりピュアに、より極上に生まれ変わった。 このアルバムを契機に彼女がアコースティックサウンドへと傾倒していくことを鑑みるに、欠かせない一枚といえる。今の彼女の原点のひとつだ。 ちなみにこのアルバム、発売当初はコンサート会場と通販のみでの販売であったが、大貫のミディ離脱後の93年にミディから、さらに96年には東芝EMIから一般発売されており、 それぞれのアルバムの収録曲には異同がある。現在最も入手しやすく、かつおすすめなのは東芝版。94年のアコースティックコンサートからの音源がプラスされている。8点。
マーティ・ペイチ指揮のストリングスオーケストラの華麗な冒頭で既に持ってかれてしまう。続いての、スリリングなモダンジャズ「Monochrome&colours」もカッコイイ。コンチネンタルタンゴ調でヴェネチアを歌った「Cavalier Servente」もロマンチック。 「或る晴れた日に」でピアノを弾く親友・矢野顕子は久々にジャズピアニストの顔を見せている。 ジャズそのものではないが、ジャズ的なソフィスケーションが盤全体に漂っている。アコースティックな作りでありながら鋭くソリッドな部分が耳に残る。才気煥発な彼女らしい。まさしく「極上のPURE」な1枚。8点。
小林武史さんが優秀なアレンジャーでプロデューサーってのはよく知ってますよ。そりゃ。でも、どうにもわたしの肌に合わないのよ。 ナチュラルなものをものすごく人工的に作っているような感じがあってだめなのよう。実験を重ね、研究し尽くして、無農薬野菜を作っているような感じ。仕上がりはナチュラルかもしれんが過程が全然ナチュラルじゃないやん、みたいな。 や。これはただのいいがかりだってのはよくわかる。でもどうにも、その作り物っぽさが、彼女の声の瑞々しさ、色気を活かすところまではいけないように見えるんだよなぁ。これからの3枚は。 坂本龍一の理知さ、冷徹さとは上手く噛み合っていたと思うけれども……。って坂本さんは一方で情熱の人だからなぁ。6点。
このアルバムで東芝EMIに移籍。東芝に移るなりいきなり、タイアップ付きのシングルとかたくさん切り出すし、作風は前作の路線でポップよりだし、で正直とまどった。 「長いキャリアのなかでこういうことに一度くらいトライしてもいいかな」。そんな思いでこの路線をやったであろうことはいまではよくわかる。質がいいのは相変わらずだけれども、ともあれ、この路線は個人的にダメなんだってば。ファンも彼女にこういうことを求めているわけじゃないと思うけれども。つーことで、6点。
徹底してポップス。どこまでも果てしなくポップス。ふっきれております。臆面もなく「しあわせのサンドイッチ」なんてタイトルをつけちゃってます。 しかし、ここまで売れ線狙いをやっても大貫妙子は大貫妙子。その引きの強さはよくわかった。 ここまでやりきって本人も気が済んだのか、この路線はひとまずここまで。6点。
ギラギラにデコラティブでないのでパッと見地味に見えるかもしれないが、よぉく見ると、厳選された高価な素材を使い、時代を選ばないそれでいてじわっと雰囲気が滲み出る意匠を凝らしている。ホンモノのおしゃれっていうのはこういうモノよ、と教えらる。7点。
結局、坂本龍一ほどのパートナーを彼女は見つけ出すことはできなかったということなのだろう。それはこのアルバムからよく伝わる。 大貫にとって坂本龍一はもっとも自分の音楽を理解している者であり、また坂本も、自分が手にしているエレメントを十全に表現できる歌手は大貫しかいない、と。鉄壁のコンビネーションだ。 坂本龍一の天才的なオーケストレーションの味わえる「TANGO」「空へ」といったところはため息しかでてこない。 それにしても無邪気に楽しそうに人につかわれている坂本龍一というのも今となってはこのアルバムくらい。 坂本人脈ということでアート・リンゼイもアレンジに参加しているが、彼は前作を踏襲するようなブラジル路線で攻めている。 またこのアルバム以降は、歌詞にも大きく注目したい。言葉に淡彩でありながらふくよかなイメージがあり、どこかこの世を達観していながらも、決してアイロニカルにはならない。彼女自身がアーティストとして、人として、円熟したからこそ書ける詞となっている。 静かに死者を悼み、人々を浄化する「Rain」は涙なしに聴くことが出来ない。 ちなみに――ジャケットのキャンパスの切れ目のようなものがどうみても女性器にしか見えない。タイトルが「LUCY=人類の母」と云うことを考えるにこれは大貫のしゃれなのであろう。9点。
また「PURISSIMA」以来、定期的に大貫をサポートしてきたフェビアン・レザ・パネもここでいよいよメインに踊りでたという感じがある。 「四季」を聞くに、気がつけばこの人も大貫妙子に欠かせない人材になっていたんだな、と。9点。
このアルバムの最大の聴きどころはなんていってもPierre Adenotのオーケストレーション。若武者のように力強く、そして瑞々しい。 「L'ecume des Jours」はまるで絵画の中に収められたある海辺の一景――絵画の中の沖の彼方の波涛が突然うねりだし、一気に迫って、額を突き破って飛沫を散らすような、そんな華麗でかつ清新な勢いを感じる。 比べて「風花」(――「四季」を引き継ぐ世界。平安歌人のごとく洗練された言葉には思わず酔っぱらってしまう)、「Espoir」の坂本龍一のオーストレーションはさながらイタリアの老大家のよう。耽美的で重厚。裳裾をずるずる引きずるような官能的な弦楽。この聞き比べだけでもこのアルバムは聞くべき。 また前作を引き継ぐLILICUBのアレンジも手堅い(――「愛を忘れないのように」の鼻っ柱の強くも可愛らしい少女っぷりがいい)し、スペインはコルテス兄弟のフラメンコギターの音色も心地いい。10点。
淡白であっさりした作り。淡淡としていて、あるかなきかのうっすらとした色彩感。とはいえ、存在感がないか、といえばそんなことはまったくない。しっかり深みと味わいがある。 少ない色でどれだけふくよかで温もりのある色彩を紡ぎ出すか、ということに挑戦したアルバムといえるかもしれない。日本人にしか理解できない、わびさびの世界。幽玄で枯淡。 なるほど、こういう50代のポップスっていうのは、アリだな。70年代の歌姫たちの到達点のひとつといえるかもしれない。7点。
おだやかで満たされた日常。しかしそれは、たくさんの汗と涙、苦しみや悲しみを乗り越えてはじめてそこにあるもの。そんなあたりまえの日常の大切さに気づかされる。 人の温みを感じるアコースティックサウンドと、彼女の綴る、派手派手しさとはまったく無縁のメロディーと言葉に、しかし、わたしは何度もはっとさせられた。 「今は あなたに会いたい 誰よりも あなたに会いたい この思い届かなくても」(「Time To Go」) こんなありきたりの短い言葉なのに、そこに千の言葉にも勝る説得力があるのだ。 今の大貫妙子は、さりげなくて、そして力強い。やさしさやおだやかさの向こうに、何者にも負けぬ強い愛と信念が垣間見える。 もう見ることのできない風景、もう会うことのかなわない人たちへ、彼女は静かに「ありがとう、さようなら」と祈りながら、しずしずと明日を信じて歩いていく。 わたしは、今の大貫妙子の歌う歌が、とても好きだ。9点。
ベテランの移籍一発目でカバーとかセルフカバーとか、近頃ほんと多いな。今回は「Shall we dance ?」や「メトロポリタン美術館」「彼と彼女のソネット」など"皆さんご存知の大貫妙子"を収録ですか。ベストアルバム的なニュアンスもってこと ? それってどうなん ? 安易でない ? そもそも96年発売の東芝EMI版の「Pure Acoustic」と収録曲被りすぎてない ? と、リリース前はぶつぶつ思っていたのだが、これ、いい。すごくいい。 弦楽四重奏、ウッドベース、ピアノ、という編成が、もう、なんて贅沢なんだろう。 音数の少ないサウンドだがしかし、豊饒としているのだ。 さりげなく、あたたかく、しかし心を捕らえて離さない訴求力がある。 テーマは「20年目の"Pure Acoustic"」、大貫にとってのアコースティックサウンドの原点「Pure Acoustic」にもう一度取り組むということだろう。 それは見事に成功したといっていいんじゃないかな。 このアルバムには"うた"がある、"こころ"がある。そして愛に満ち溢れている。こんな素敵な歌手になっていたんだね、彼女。強くって、大きくって、こんなにもやさしい。 これって蛇足なんじゃ、と聞く前は思っていた後半(M.10〜14)の87年の「Pure Acoustic」からの再収録部分も、これもなかなか効果的。 続けて聞いていくと、後半と前半の違いでどのように彼女が成長し円熟していったのかがよくわかる。 まだ87年の段階では、歌唱も演奏も良くも悪くも脂っこいのだ。それはそれで見事ではあったが、自意識が強くてまだ音にほんの少し雑味があった。 それが20年経て、ほんとうにまさしく枯淡の境地へと彼女は達した。淡々としているのに、どこまでも深みがある。 大貫妙子という歌手を知らない人に最初に薦めるのは、この一枚がいい。最高。 ちなみに。このアルバムのA&Rディレクターは、80年代に南野陽子、原田知世を担当した吉田格さん。こんなところで名前を拝見することになるとは。10点。
様々な経緯で生まれた作品をまとめており、なかには、作詞作曲なしボーカル参加のみ、という作品もあるのだけれども、オリジナルアルバムのような統一感がでているのはさすが。 もちろんセレクションのセンスもあるのだけれども、30数年大貫妙子のアーテイスト活動のぶれなさというのにも舌を巻く。どんな企画的な作品であっても、常に大貫妙子は大貫妙子なのだなと。小器用に相手にあわせることなく、愚直なまでに自らを貫く姿勢に敬意を持たずにはいられない。 「LUCY」以降特に強くなった、静謐さとはるかなるものへの祈念の強い、おおきな歌が光っている。「note」収録時にはあまり意識のしなかった「snow」が特にしみる。MISIAの「名前のない空を見上げて」、ユーミン「私のフランソワーズ」の自分のものにさせっぷりも凄い。細野晴臣「ファム・ファタール」の上品な小悪魔っぷりもなかなか。この出来をみるに大貫妙子のカバーアルバムってのもアリかなと思えるけれども、彼女がその企画にうなづかないだろうな。90年代後半から現在にかけての大貫妙子の世界が端的にあらわれた一枚といっていいかと。8点。
00年の「アンサンブル」以来のゴールデンコンビの復活――というアルバムなのだろうけれども、坂本龍一の勢いがいささか足りないように聞こえる。そして、大貫がかなり坂本の世界に歩み寄って表現しているようにも聞こえる。酷いいい方をすれば老いて覇気のなくなった坂本に旧知の大貫が介護補助のように歩調を合わせてつきあってあげている、そんな印象。「何か新しいもの」をこのアルバムに私は感じ取れなかった。 大貫のアコースティックサウンドへの傾倒は87年の「pure acoustic」からはじまり、近年のアルバム「note」「One fine day」 「Boucles d’oreilles」でも一貫した流れがあったわけだけれども、それらのアルバムが総じて人肌を感じるヒューマンで暖かな印象を聞き手にもたらすのを対照的に、今作は孤独で、冷たく冷えていて、陰鬱だ。色でいうなら、ここ数年の作品が暖色系とするなら今作は寒色系という感じ。 これは明らかに坂本のカラーに合わせてのことなのだろうけれども、そこから大貫がやりたいことが、近年のこれまでの作品と比べてクリアに見えない。坂本は、ちょっとこれ、まったくのノープランなんじゃないかなー。大貫の既発表曲のリアレンジとか、もっと闘争心燃やしてもいいものを、なんか無難に置きにいってる感じ。「四季」も「夏色の服」も「風の道」も元アレンジの方がいいぞ、これじゃ。音楽家として超えてるふたりなのだから、もちろん一定のクオリティーは保持しているのだけれども、スリルがない。なんかこう、ものすごい老後感が漂ってしまっている。未来が感じ取れない。 ミニマルなピアノと女性ボーカルというコンセプトのアルバムを坂本は82年に加藤登紀子「愛は全てを赦す」でトライしているけれども、こちらは気迫に満ちていてスリリングだったのだから、サウンドコンセプトのせいだけではないのだろうな、おそらく。 野蛮で兇暴で矛盾に満ちていてどっか壊れてる、そんな80年代の坂本龍一に戻ることは出来ないのかも知れないけれども、うーん。厳しい。この二人をしてこんな生気のないアルバムが出来てしまったことに驚愕した。80年代を華やかに生きたスノッブな業界人たちにとって、今は厳しい時代なのだろうけれども……。7点 |