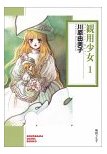
|
川原由美子
「観用少女(プランツ・ドール)」 美しき童形の神 (朝日ソノラマ/1995〜/1〜4巻) |
プ、プ、プ、プランツドーーールッッ!!!! ……はぁ……はあっ。 読み終わった途端、思わず拳をあげて叫んでしまったよ。 今日は学校の美術の宿題にメンマでモビールを作った川原由美子さんの「観用少女(プランツ・ドール)」の話。 吾妻ひでおがネタに使ったりとか、前々からこの作品の存在とそのコンセプトは知っていたけどね。まさかここまでの直球の作品とは。 舞台はちょい近未来。 この世のものと思われぬ美しさを持ち、ミルクと砂糖菓子と愛情を糧に成長する、生きる人形「観用少女(プランツ・ドール)」。 その極上の笑みに魅せられた人々の哀歓の物語。 って感じの、1話完結の連作モノですわ。 まあ、この説明だけで、あんなんや、こんなんだろうって想像されると思いますが、そう、その通りです。 だいたいにおいて間違っていません。 SF・ファンタジーとしてみたら、限りなくワンアイデアモノなんだけど(―――萩尾望都とか大島弓子ならせいぜい100ページ前後の中篇で落とすようなネタですな)、現実世界からすりガラスの一枚で隔てられた穏やかな安住の世界、という典型的少女漫画的視点で描かれているので、その物語とならないような穏やかな物語も、大人に成長しない「観用少女」そのものともいえ、似つかわしく感じる。 アイドルとかに深く入りこんだりと、美しいものを溜息交じりに愛でることに関しては人後に落ちることのない私なので全然オッケー―の世界です、はい。 これは「愛する者の物語」だと思う。 「観用少女」がいかなる生き物で彼らは何を思い、何を感じ生きているのか、そういった実存的な部分はまったく触れない。 ただ神々しいほど美しい微笑みを見せる異なる世界の者として「彼岸で輝くもの」として彼女らは描写される。 でもって、物語の骨は絶えずその微笑を享受する庇護者に寄っている。 ――この辺が萩尾らとは全然違うところだろうな、24年組作家ってのは結局「愛される者の論理」ってのが最終的局面ではどこか出てくる。 女性の実存を見るとき、絶対「愛される/愛す」の構造ってのは絶対避けて通れないものがあるしね。 ということで、逆にいえばこの「観用少女」という物語はきわめて男性的な論理による少女讃歌モノともいえる。 っつーか、そんなこといわんでも直感で「なんだこの野郎向け同人誌みたいなロリータ直球のテーマ」はっっ、て誰しも思いますがね。 わたしゃ、一読して「こんなところにもナボコフの末裔がっ」と思いましたよ。 とにかく観用少女があらゆる物を押し退けて圧倒的なまでに、美しい。 その微笑みは、この世のあらゆる矛盾や汚辱を浄化し、煩悩を昇華する。 彼女らの微笑みがそのまま世界と等価値である、といってもいいほど。 と、ぐねぐね思っているうち、ふと「童神」「小さ神」という言葉が頭をよぎった。 神仏が小童の形態において示顕するってのは民俗学の祖、柳田國男、折口信夫などの手による有名な論証のひとつである。 つまり稚児の姿こそそのまま神の姿である、稚児は神仏の化身である、小ささこそがその霊性・神性の証である、ということである。 この「観用少女」も永遠の少女であるがゆえの圧倒的な霊性をもって、庇護を受けながらもその庇護ゆえに庇護者に福音をもたらす存在として描かれている。 また性的なニュアンスを匂わせながらもどこまでもスピリチュアルな高みの位置から落ちない存在というのも「小さ神」そのものである。 これは1種、性愛と信仰の綯い交ぜの状態ともいえるわけで、であるから第4巻・第2話の「プレゼント」の回のように観用少女が天使の様に純白の羽を持つのも蓋し納得である。 となると「観用少女」と「人間」の関係はそのまま「小さ神」と「育て神(――扶育、臣従、補佐の役割)」の関係と同質といえるだろう。 と、この物語には千年単位の民族的な神のイメージがそのまま生きているといってもよく、またこれは「少女漫画文化」の底流に流れている――例えば「やおい」に置ける「美少年」と「年長の庇護者」の関係はほとんどこれにあたるといっていい、ということを最後に付け加えたい。 と、無理やり民俗学と漫画を大塚英志バリに結び付けて見ました。 こうすると評論みたいでしよ。 |
2003.11.12