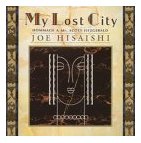ああ、夜毎の乱痴気騒ぎの20年代よ。 爛れ崩れ落ち、甘い香を放つ果実のごとき20年代よ。 黄昏の黄金の陽の輝きのごとき20年代よ。 我は君を愛す。 ◆ 1920年代をテーマとした音楽作品というのは多いが、そのなかで最も愛するもののひとつが、久石譲の「My Lost City」である。 このアルバムはスコット・フィッツジェラルドへのオマージュであり、1920年代のデカダンスを再現したアルバムである。 タイトルになっている「My Lost City」はフィッツジェラルドの作品名に拠っている。フィッツジェラルドの「My Lost City」は自らの半生と彼の愛すべき失われた街、ニューヨークを重ね合わせた掌編である。 ここで当時のアメリカ、ことにニューヨークの事情を説明しなければならない。 アメリカにとっての1920年代とは第一次世界大戦の終焉と禁酒法の制定にはじまり、1929年10月24日の暗黒の木曜日で終わる、過発展と狂乱の10年であった。 戦後、第一次世界大戦の戦火を免れたアメリカには移民が急増する。その大量に流入した労働力によってアメリカは未曾有の経済発展を迎える。 その空前の好景気は過剰消費、過剰生産による世界ではじめての大衆社会を生み出すに至った。大量の人、モノ、情報が集り、大衆の欲望がダイナミックにぶつかる世界である。 現代もつづく高度消費社会・大衆社会の基点はここにあるといっていいだろう。 車社会の確立―――1915年に250万台の車の登録台数が25年には2000万台にまで急増、人の行動範囲をかえた。 月賦制度の確立―――その車を簡便に購入するために生まれたのが月賦制である。これが個人生産と個人消費のサイクルを変えることになる。 ラジオの放送開始、映画館の急増、ブロードウェイの繁栄―――現在に至るマスメディアと商業芸術がこの時確立され、それと同時にマスメディアによって生まれたヒーロ―もこの時誕生する。野球のベーブ・ルースやボクシングのジャック・デンプシー、リンドバーグもそうしたヒーローの一人であったし、若くして死んだルドルフ・バレンチノの葬儀には十万人ものファンが列をなした。さらにラジオから人はその日の情報を即座に受け取ることを可能にし、情報のスピードに革命をもたらした。そのラジオで流れていた新しい音楽がジャズであった。 さらに、旧来の道徳律の否定。流行という強迫的概念。社会進出していく女性。マスメディアのスキャンダリズム。高層ビル群(摩天楼)の乱立……。現代の都市社会の潮流の端緒が全て出ているといってしまってもいいだろう。 日々が祝祭のような狂躁的なこの10年のアメリカを別名「ジャズ・エイジ」と呼ぶ。 ―――「ジャズ・エイジ」それは、アメリカにとって世界にとってはじめてのバブルであったわけである。 80年代末期の日本の経済が空転していったのと同じように、1920年代後半のアメリカの経済も実質の富の限度を越えて空転していく。 自動車の普及で、通勤圏や行動範囲が広がったことによって建築ブームが大都市郊外にまで及ぶようになり、異常なまでの土地の急騰を引き起こす。 地価の急騰、常に大量消費される物資、好景気への信頼を過信した大衆は男女、労働者・企業家の別なく、自由になる金を株式の運用にまわすようになる。その時に役だったのが、オンタイムで情報が刷新させる新メディアであるラジオであった。 1927年のニューヨークのせわしなさは、ヒステリーの一歩手前とでも評すべきものであった。 いつまでの上向きの経済、いつまでの右肩あがりの地価・株価、どこまでも発展し、どこまでも成長し続けるであろう。なぜならここはまだまだ若き「新世界」なのだから。 誰もがそう思い込むことによって実質のそれ以上へと景気は膨らんでいった。バブルである。 その幻想はある日突然、崩壊した。それが1929年10月24日、「暗黒の木曜日」である。この瞬間アメリカにとっての黄金の20年代は幕を下ろす。 その狂乱の時代を代表する旗手として現れたのが、まさしくスコット・フィッツジェラルドであった。 彼は「ジャズエイジ」の体現者として表舞台に現れ、「ジャズエイジ」の終焉と共に失墜していった。時代と心中したまさしくジャズエイジの作家である。 彼は20年代のはじまりである1920年に「楽園のこちら側」で「ジャズエイジ」の寵児として彗星のごとく登場する。その成功をきっかけに奔放な少女、ゼルダと結婚。 2人で放蕩と頽廃の懶惰な日々を重ねながら小説を濫作、渡欧し当時のフランスに集った様々な芸術家と邂逅、そこで「偉大なるギャツビー」という長編を書き、名声は天に上ったが、二人の甘い生活を終わらなかった。 そして1929年、あの時代が突然終わりを告げたのと同じく、彼の黄金時代も終幕となる。妻・ゼルダの発狂。 最愛の妻は狂気に陥り、彼は酒に溺れる。稿料は10分の一以下になり、ほとんどの著書が絶版となり忘れ去られた。 そこでこのままではいけないと一念発起。長編『夜はやさし』の執筆を始めるためにニューヨークを離れる彼がニューヨークという街へ贈ったはなむけの言葉、それが「My lost city」という掌編になる。 ここに描かれているのはニューヨークの黄金の十年の追想である。 彼はこの掌編の終章で不況にくすんだニューヨークの街へ向けてこのような言葉を告げる。 そして今、私はこの失われてしまった私の街に別れを告げよう 彼は新たな扉を開くためにもう今は失われてしまった過去の街へと決別するのである。 この沈みゆくかつて黄金であった街と共におちてゆくのではなく。もう一度、新たな生き直すために。本当の文学者としてやりなおすために。 しかし、彼の新たな文学的挑戦の結実となった「夜はやさし」は、大衆からは無視というかたちでの評価を受けただけだった。彼の絶望と転落はニューヨークという街を去ったこれからが本番だったといえる。 日々の生計のために売文を重ね、ハリウッドに脚本家として流れ着いたところ、40なかばで彼は亡くなる。 彼の転落は全て予定されていたことかのように、粛々と奈落に落ちていったように私には見えてしかたない。 1929年に迎えた突然の暗黒期の到来は彼にとっては当然くるべき結末であり、その後訪れる苦渋の日々もまた当然の帰結である、と私には映る。 もちろん、彼自身はそんなことないとこの残酷な時代の歯車に対して無様で悲惨な戦いを挑むようになるのだが、それすらも予定のうちに後世の者からは見えてしまう。 日本の文学者のこの残酷な言葉がそれを物語っている。 もっとも「時代の申し子」としてのフィッツジェラルドの真価は、その栄光のなかにでなく、1929年の大恐慌と時期を同じくする彼自身の崩壊の中にある。アメリカのアドレセンスの崩壊と彼の夢の崩壊、それは実に見事な崩壊であった。彼は崩壊するために栄光を築き上げ、そして自身が崩壊することによって彼とその作品は時代に封印された。 ゆえに彼の著作は名作として後世に作品と名を残すまでになった。 彼と彼の作品は崩壊があってはじめて完成形となりえたのではなかろうか。 事実、彼は人気の絶頂の時でも今自分に訪れているあらゆる幸福が砂上の楼閣であることをどこか自覚しているかのような、そんな冷徹さと不安感がいつもそこにあった。そしてそれが作品に独特の哀感を伴わせていた。 私は言葉にならぬ声で叫び始めていた。そうだ、私にはわかっていたのだ。自分が望むもの全てを手に入れてしまった人間であり、もうこの先これ以上幸せにはなれっこないんだということが。 ―――これ以上もう、幸福になんてなれっこない。この真昼に暗闇を見てしまった者のような一見間抜けで贅沢なこの絶望は、彼個人のパーソナルな絶望でもあり、そしてまたニューヨークっ子の、ジャズエイジを生きた者の全てを象徴する絶望でもあった。 まぁ、ここでフィッツジェラルドのことをこれ以上ういういと語ってもしたかない。 狂乱の日々の果て、美しき少女はいつかこころを病み、不遜なる若者は酒に溺れる。人は去り全ては遠のく。 失寵の天才に神から与えられる気まぐれな霊感、鮮やかな幻は更に彼を奈落の底へと落とした。 彼は物語の断片だけを残して死に、残られたかつての少女は精神病院で焼け死ぬ。 時代という避けがたき運命の糸によって翻弄されたひとりの若き作家のそれが顛末である。それだけを念頭にいれていただきたい。 話を久石譲のアルバムに戻す。 このアルバムで描かれているのは、1920年とその後という時代を生きたフィッツジェラルドとゼルダの道行のようなアルバムに映る。 二人は時代の運命の糸に操られるままに奔放を演じ、頽廃を演じ、悦楽を演じ、狂気を演じ、失墜を演じた。 彼の言葉を借りれば「囚人達が囚人服のデザインを選べないように」2人もまた、その役を降りることはあたわなかった。 時代という舞台は残酷なまでに絶対である。ふたりは自らの至る道が破滅であることが百も承知でありながら1歩ずつその奈落への階段を降りていった。 その1歩ずつのきざはしがこのアルバムの1曲ずつに収められているように私には感じる。 このアルバムのメインテーマである「漂流者 〜DRIFTING IN THE CITY〜」は圧倒的なまでの荘厳さと悲劇性を持った名曲である。 久石の生来の持ち味のロマンチックな旋律にデカダンな風合いが重ねあっている。 ピアノとストリングスがある時は追いかけあうように、ある時は静かに寄り添うように巧みに絡み合うさま。それはまるで螺旋のかたちで急降下するようであり、破滅の美しさに似ていて、わたしは思わず眩暈がする。 続く「1920 〜age of illusion〜」はまさしく20年代のもうひとつのテーマである。パワー・スピードが絶対である表層美の時代の胎動を力強く表現している。ここに頽廃の影はない、常に成長し輝き続ける、それが信じることの出来た時代の曲だ。 この裏表の2つのテーマのむこうにあるのが、20年代である。 更に続く「Solitude 〜in her…」「Two of us」「Cape Hotel」といった楽曲は全て淡々と悲しく孤独が染み入るようである。ロマンチシズムとデカダンスとノスタルジー、これがこのアルバムの基調といえよう。 メランコリックでノスタルジックで雲母がキラキラしているように美しく、はかない。 また情熱的なアルゼンチンタンゴの「TANGO X.T.C.」「Jealousy」もやさしく悲しい音色だ。消えかけの熾火を無理やり掻きまわして、束の間だけ燃えあがるようなそんな虚しさが漂っている。 2人の男女はかくなるように1曲毎に安住を求め、都市をさまよう。しかし、2人は根無し草である。安住の地などはどこにもない。ただ、虚しく彷徨をかさねるしか生きる術はないのだ。 「漂流者 〜DRIFTING IN THE CITY〜」のメロディーが再び物悲しく聞こえて、この盤は終わりである。―――ラストの「漂流者 〜DRIFTING IN THE CITY〜」のバリエーションがアルバムタイトルの「My lost city」というのが洒落ているな、と感じる。物語のエンドマークのようにこれが響くのだ。 私はこれをしっている。 この旋律を、このハーモニーを、この浪漫、この悲劇、この美しさを。 はじめてこのアルバムを聞いた時、音の波動にのみこまれた瞬間、陶酔と共に懐かしさが心の底から湧きあがってきたことを私は覚えている。 手放しで泣きたくなるような懐かしい愛しい悲しさがこのアルバムにはあった。 このテキストを書く折りにこのアルバムを流しっぱなしにしていたが、今でも、やはりオープニングは体中がしびれたようになる。この音の中に沈んでいきたくなるような気分になる。 このアルバムが日本のバブルであった80年代を過ぎた92年にリリースされたというのは久石譲の計算だろうか、それともはたまたただの偶然だろうか。 冷戦下、核戦争の恐怖を裏に隠しながら、胞衣のゆりかごの中のごとく経済的な成長をつづけ、その頂点を迎えた80年代の日本と、 2つの大戦にはさまれ、様々な矛盾を内包しながらも経済発展をおしすすめ、一時の爛熟を迎えた1920年代のアメリカはよく似ているように感じる。 冷戦が終わりをつげ、日本では好景気が終わり―――俗に言えばバブルがはじけ、日本経済が失寵の坂道をまさしく転がり落ちはじめた1992年にこのアルバムがリリースされたというのは出来すぎのように私には映る。 しかも破滅の予兆を常に孕みながらも時代を謳歌し、はたして時が過ぎ、予兆のとおりに破滅していったフィッツジェラルドに奉げた作品、というのも、あまりにも話が上手すぎる。 このアルバムは、失われた過去の光芒である20年代の葬歌でもあり、そして80年代の黄金時代の日本への葬歌とも私には響く。ただ、このアルバムにある20年代のように日本の80年代は美しくはなかったのだが……。 ちなみに久石譲はリーダーアルバムを数多く出しているが、そのほとんどが彼の担当した映画音楽やCM音楽のコンピレーションであったり、そういったものを装いを新たに録音したものであったり、また未発表の新作をひとまずつめ合わせたモノであったりと、そうした雑多なものが多いなかで、このアルバムは珍しくコンセプトアルバムとなっている。 このアルバムでも「紅の豚」「はるかノスタルジー」「ふたり」といった映画で既に発表された楽曲が収録されているが、それらは全てコンセプトに基づいたものである。彼にはまたこうした独特の世界を持ったアルバムを再び世に出してほしいな、とわたしは思っている。 |